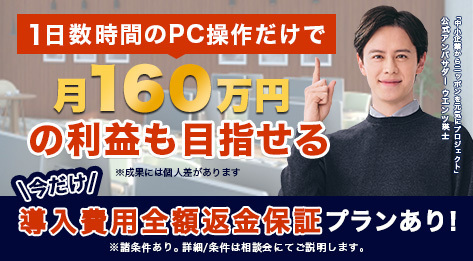減価償却とは?メリット・デメリットから計算方法まで詳しく解説!
最終更新日:2020年12月17日

経営者やフランチャイズオーナーを目指すのであれば、「減価償却」に関する知識はきちんと身につけておくことが大切です。特に中小企業に該当する場合は、正しい知識を持っているかどうかで会社のキャッシュフローが大きく変わることもあります。
そこで今回は、該当する資産や耐用年数、計算方法など、減価償却の基礎知識を分かりやすくまとめました。
減価償却とは?
減価償却とは、法人や個人事業主が特定の固定資産を購入したときに使う勘定科目のこと。勘定科目としては特殊な部類であり、ほかの科目と比べると以下のような違いがあります。
- 1つの固定資産の経費を、複数年にわたって計上する
- 購入した固定資産の種類によって、計上のルールが変わる
固定資産の種類によって計上方法が変わる理由は、対象物(※以下、減価償却資産)の「耐用年数」に応じて費用計上をするためです。日本では減価償却資産ごとに耐用年数が定められており、例えば耐用年数が4年と定められているパソコンを購入した場合は、その購入代金を4年間にわたって費用計上をします。
では、具体的にどのようなものが減価償却資産に該当するのか、以下でいくつか例をご紹介しましょう。
| 減価償却資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| 事務机(金属製) | 15年 |
| 計算機や複写機 | 5年 |
| 厨房用品(ガラス製) | 2年 |
このように、減価償却資産はその種類によって耐用年数が大きく異なります。
減価償却の目的
減価償却の目的は、「費用収益対応の原則」を実現することと言われています。
費用収益対応の原則とは、期間収益と期間費用の金額にきちんとした相関性を持たせるために、期間に応じた費用計上を目指す原則のこと。例えば、高額な設備の購入費用をすべて当期分の経費として計上すると、当期の支出が増えすぎたり、翌期以降の黒字が膨らみすぎたりしてしまいます。
そこで考え出された勘定科目が、今回解説している減価償却です。減価償却資産の購入費用は、耐用年数に応じて複数年をかけて計上されるため、高額な設備などを購入しても期間収益と期間費用のバランスがきちんと維持されます。
つまり、減価償却は企業の業績を正しく、より実態に近い数値に近づけるための制度と言えるでしょう。
減価償却のメリット
減価償却を導入すると、実は企業側にも以下のようなメリットが生じます。
- 会社の経営状態を細かく把握できる
- 節税効果を得られる
- 翌期以降の見かけ上の社内留保を増やせる(自己金融効果がある)
減価償却を利用することで業績が実態に近づく点は、企業にとっても大きなメリットです。業績が実態に近づくと、経営状態や毎期の損益を正しく把握できるので、より質の高い事業計画や経営計画を立てやすくなるでしょう。
また、減価償却を利用すると、複数年にわたって資産の購入代金を費用計上できるので、翌期以降の法人税を抑えることにつながります。一方で、高額な資産の購入代金を一括計上すると、当期の経費が膨らみすぎたり、翌期以降の利益が増えすぎたり(=法人税が増える)といった弊害が生じるでしょう。
最後に、見かけ上の社内留保を増やせる点も、減価償却に関して経営者が押さえておきたいポイントです。例えば、1,000万円の購入代金を5年間にわたって減価償却する場合、毎期の減価償却費は200万円(1,000万円÷5年間)になります。このとき、資産を購入した当期には1,000万円の支出があるものの、翌期以降には200万円の支出が実際に発生するわけではありません。
そのため、翌期以降の会計では、200万円分の「見かけ上の社内留保」が増える形になります。あくまでも会計上の数値であるため、実際に同じ額の現金が増えるわけではありませんが、この仕組みをうまく活用すれば外部に対して財務状況を良く見せることも可能です。
減価償却のデメリット
減価償却を利用しても、企業側には税制上のデメリットは発生しません。ただし、多くの減価償却資産を購入した場合には、会計処理に大きな手間がかかってしまう恐れがあります。
前述の通り、減価償却資産にはそれぞれ耐用年数が定められており、減価償却費を計上する際にはその耐用年数を資産ごとにチェックすることが必要です。特にリース会社や不動産管理会社などは、減価償却資産を購入する機会が非常に多いので、余裕をもって会計処理に取りかかる必要があるでしょう。
減価償却できる資産・できない資産
減価償却を正しく理解するには、「減価償却できる資産」と「できない資産」をしっかりと把握しておくことが必要です。固定資産と聞くと、なかには減価償却をイメージする方もいらっしゃいますが、すべての固定資産が減価償却資産に該当するわけではありません。
購入した資産が減価償却資産としてみなされるには、主に以下の条件を満たすことが必要です。
- 業務に使用する資産であること
- 時間の経過によって劣化する資産であること
では、実際にどのようなものが該当するのか、減価償却できる資産・できない資産の具体例をいくつかご紹介していきましょう。
| 減価償却できる資産 | 減価償却できない資産 |
|---|---|
| 建築物、機械装置、車両、工具、ソフトウェア、パソコンなど | 土地、美術品、骨董品、電話加入権など |
例えば、土地や美術品、骨董品などは、時間の経過によって価値が下がるものではないので、業務に使う場合であっても減価償却資産には含まれないことになります。
中小企業の場合は特例も
実は減価償却には、中小企業にのみ適用される特例があります。現時点では令和4年3月31日までの期限付き特例ではありますが、この特例を利用すると30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)を購入した場合に、当期中の経費として一括計上することが認められます。
ただし、この特例の適用を受けるには、以下の要件を満たさなくてはなりません。
- 青色申告法人であること
- 確定申告書等に明細書を貼付して申告をすること
- 当期中の少額減価償却資産の合計額が300万円以内であること
この特例は将来的に延長される可能性があるので、中小経営者になる予定の方はこれを機に制度の詳細をしっかりとチェックしておきましょう。
減価償却の計算方法
減価償却には複数の計算方法があり、どの方法を選ぶのかによって毎期の償却額が変わってきます。では、具体的にどのような方法があるのか、以下で3つの計算方法をご紹介していきましょう。
定額法
定額法は、減価償却資産の購入代金を耐用年数の期間で同額ずつ償却していく計算方法です。つまり、償却額が毎期同じ金額になるので、今回ご紹介するなかでも最もわかりやすい計算方法と言えるでしょう。
定額法による償却額=取得原価 × 定額法の償却率
※定額法の償却率=1 ÷ 耐用年数
例えば、耐用年数が10年の資産を100万円で購入した場合、定額法による償却額は10万円(100万円×0.1)となります。したがって、この資産は1期ごとに10万円ずつ償却していきます。
定率法
定率法は、資産の購入代金を一定の割合で償却していく計算方法です。減価償却資産を購入した期に最も多くの金額を償却し、期が進むごとに償却額が減っていく計算方法と考えれば分かりやすいでしょう。
定率法による償却額(1期目)=取得原価 × 定額法の償却率
定率法による償却額(2期目以降)=取得原価の残額 × 定額法の償却率
基本的な式は上記となりますが、償却額が償却保証額(取得原価×保証率)を下回る場合は、「取得原価の残額×定額法の改定償却率」の計算式によって償却額が計算されます。
上記のうち「定額法の償却率」や「保証率」、「改定償却率」については、国税庁が公式ホームページ上で資料となる表を公開しているため、計算をする際には事前にチェックしておきましょう。
級数法
級数法は、定率法の簡便法として位置づけられている計算方式です。計算式は以下のように異なるものの、定率法と同じく期が進むごとに償却額が減っていく特徴を持っています。
級数法による償却額(1期目)=取得原価 × 級数法の償却率
級数法による償却額(2期目以降)=取得原価の残額 × 級数法の償却率
※級数法の償却率={耐用年数-(経過年数-1)} ÷ {耐用年数 × (耐用年数+1)÷2}
実は現行の法人税法では、級数法による減価償却額の計算は認められていません。2020年現在では、上記でご紹介した定額法・定率法による計算が主流なので、まずはこの2つの計算方式をしっかりと理解しておきましょう。
減価償却を計算する際のポイント
減価償却の計算をする際には、主に「耐用年数・取得原価」の2つの数値を用います。では、これらの数値がそれぞれ何を表すのかについて、以下で詳しく解説をしていきます。

耐用年数
「耐用年数」とは、購入した資産を使用できる期間のことです。耐用年数は減価償却資産ごとに定められており、減価償却費を計算する際には各資産の耐用年数をしっかりとチェックしておく必要があります。
そこで以下では、フランチャイズ開業で使用することが多い減価償却資産について、それぞれの耐用年数を簡単にまとめました。
| 減価償却資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| 事務所用の建築物(鉄筋コンクリート造) | 50年 |
| 応接セット(接客用) | 5年 |
| 冷房機器・暖房機器 | 6年 |
| 冷蔵庫やガス機器 | 6年 |
| カーテンなどの繊維製品 | 3年 |
| 室内装飾品(金属製) | 15年 |
| 電話設備や通信機器(デジタル) | 6年 |
| 時計 | 10年 |
| 手さげ金庫 | 5年 |
| 光ディスク | 6年 |
上記でご紹介した耐用年数は、あくまでも一部の減価償却資産のものです。ほかにも数多くの資産について耐用年数が定められているため、固定資産を購入した際には国税庁のホームページなどで都度チェックをしておきましょう。
取得原価
取得原価とは、資産そのものの代金である「購入代価」と、購入の際に発生する「付随費用」を合計した金額のことです。領収書を見れば確認できる数値ではありますが、購入代価に手数料などの付随費用を加える必要があるため要注意です。
例えば、購入代価が100万円の車両を購入したときに、追加で3万円の運送費が発生した場合の取得原価は、103万円(100万円+3万円)になります。購入手数料や運送費のほか、仲介手数料や関税、保管費、購入事務費なども付随費用に含まれるので、資産購入の際に発生したコストは細かく確認をしておきましょう。
残存価額
最後に、平成19年3月以前まで減価償却費の計算に用いられていた、「残存価額」についても簡単にご紹介します。残存価額とは、簡単に言えば耐用年数分使い切った減価償却資産の処分価額のことです。
かつて、この残存価額は「取得原価の10%」として計算されており、減価償却費の計算式に用いられていました。しかし、平成19年度に税制が改正された影響で、2020年現在では残存価額という概念自体が用いられなくなりました。
その代わりに、いまでは「残存簿価」と呼ばれる概念が用いられており、耐用年数分使い切った資産の処分価額は1円として取り扱われています。
減価償却の仕訳方法
減価償却の仕訳方法には、「直接法」と「間接法」の2つがあります。どちらを選んでも納めるべき税額は同じですが、自社に適した方法で会計業務を進めたいのであれば、それぞれの違いをきちんと理解しておくことが重要です。
そこで以下では、直接法と間接法の違いを簡単にまとめました。
直接法
直接法は、固定資産から減価償却費を直接差し引く仕訳方法です。以下のように、借方に減価償却費を、貸方に固定資産を記載するシンプルな仕訳なので、会計に慣れていない方でも分かりやすい方法と言えるでしょう。
(※取得原価100万円、耐用年数5年の応接セットを、定額法で償却した場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費:20万円 | 応接セット:20万円 |
上記の仕訳は、減価償却費によって固定資産の残高が20万円分減ったことを意味します。つまり、毎期の仕訳をチェックすれば、直接法では「あといくら費用にできるのか?(固定資産の残高)」を簡単に把握できます。
間接法
間接法は、貸借対照表にこれまでの償却額の累計金額を記載するために、償却額を「減価償却累計額」として計上する方法です。貸方に記載する内容は直接法と同じですが、以下のように貸方には「減価償却累計額」と記載します。
(※取得原価100万円、耐用年数5年の応接セットを、定額法で償却した場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費:20万円 | 減価償却累計額:20万円 |
なお、上記のような個々の仕訳では、減価償却累計額には1期分の償却額を記載します。これまでの累計額については、あくまでも貸借対照表に記載することになるので注意しておきましょう。
ちなみに、間接法はその性質上、個々の仕訳や貸借対照表からより多くの情報を読み取れる特徴を持っています。そのため、多くの固定資産を購入する企業や、事業に固定資産が深く関わってくるような企業では、間接法による仕訳が望ましいと言えます。
税制改正のタイミングでは、その都度ルールの確認を
減価償却のルールは税制改正とともに変わってきており、例えば平成19年度以前と現在とでは、計算方法に大きな違いがあります。将来的にルールが変更される可能性も考えられるので、税制が改正されたタイミングでは現行のルールをしっかりと確認しておくことが大切です。
また、中小企業を運営する経営者については、本記事でご紹介した特例の詳細もしっかりとチェックしておきましょう。
公開日:2020年10月20日