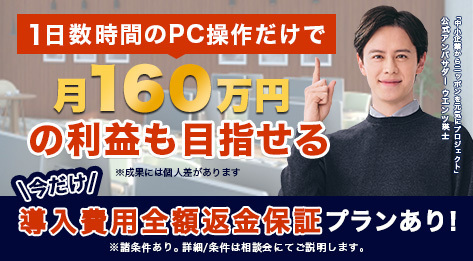収入印紙とは?収入印紙が必要な金額や割り印方法をご紹介!
最終更新日:2020年12月17日

領収書をはじめ、ビジネスシーンではさまざまな文書に収入印紙を貼る必要があります。印紙税が必要になる文書は種類が多く、さらに種類によって納めるべき金額が異なるので、つい混乱してしまう方も多いことでしょう。
そこで今回は各文書の印紙税額など、収入印紙に関する基礎知識をまとめました。割り印の正しい押し方についても詳しく解説しているので、自信のない方はぜひ最後までチェックしてみてください。
収入印紙とは?
日本国内では一定金額を超える領収書や契約書、有価証券などをやり取りする場合に、印紙税を納めることが義務づけられています。この印紙税を納めるために、対象となる文書に貼る証票のことを「収入印紙」と言います。
収入印紙は郵便局や法務局、コンビニなどで簡単に購入できますが、「誰が印紙税を負担するのか?」という点は正しく理解しておかなくてはなりません。基本的には文書の作成者に納税義務があるため、領収書の場合は商品・サービスの販売者が収入印紙を貼ることになります。
一方で、契約書の場合は最終的に必要な額の収入印紙が貼られていれば、印紙税はどのような割合で負担しても問題ありません。ただし、日本ではお互いが作成した契約書をそれぞれ保管するケースが多いため、契約書の印紙税については双方が平等に負担する形が一般的となっています。
なお、印紙税が課せられない官公庁と契約を結ぶ場合は、民間側がすべての印紙税を納める必要があります。国や地方公共団体をはじめ、「非課税対象団体」と契約を結ぶ場合はすべてこのケースに該当するため、民間同士の契約と混同しないように気をつけましょう。
印紙税が課される書類(課税文書)とは?
印紙税が課せられる書類は「課税文書」と呼ばれており、この課税文書は20の種類に分けられています。とは言うものの、実務で使用する文書は限られているので、以下ではビジネスシーンでよく使用される3つの課税文書について詳しくご紹介していきましょう。
領収書(受取書)
商品やサービスに関する領収書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として課税文書(第17号文書)に含まれています。税額については以下のように、領収書に記載された受取金額によって変動するため注意が必要です。
| 受取金額 | 課税金額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超~3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載がないもの | 200円 |
ちなみに上記の「受取金額」はあくまで本体価格のみであり、税抜での価格となります。例えば、消費税によって税込価格が5万円を超える商品を売買した場合であっても、本体価格が5万円未満であれば印紙税は非課税となります。
ただし、領収書上で税込・税抜を判断できない場合は、すべてのケースにおいて税抜価格として扱われてしまうので、税込の領収書をやり取りする際には「52,000円(消費税込み)」のように明記しておくことが望ましいでしょう。
領収書(受取書)への収入印紙を貼り忘れた場合は?
税務調査において、領収書への収入印紙を貼り忘れたことが発覚すると、「本来納めるべき印紙税の3倍の金額」を納める罰則が科せられます。例えば、受取金額が300万円の領収書に収入印紙を貼り忘れた場合は、合計で3,000円(本来は1,000円)の印紙税を負担しなければなりません。
ただし、税務調査で指摘を受ける前に申告をした場合は、罰則が「本来納めるべき印紙税の1.1倍の金額」に軽減されます。そのため、収入印紙の貼り忘れに気づいたらその課税文書について確認を取り、すぐさま所轄の税務署長に申し出るようにしましょう。
収入印紙がない領収書を受け取った場合は?
では、収入印紙がない領収書を受け取ったときには、どのような対応が必要になるのでしょうか。前述の通り、この場合の納税義務者は領収書の発行者となるので、自社側で収入印紙を新たに貼り付ける必要はありません。
仮に税務調査において収入印紙の貼り忘れが発覚しても、このケースでは領収書の発行者側に罰則が科せられます。さらに、収入印紙がなくても領収書自体が無効になることはないので、発行者に対して連絡を入れなくても特に問題はないでしょう。
ただし、領収書の発行者と今後も長く取引をする場合は、良好な関係を築くために連絡を入れておくことをおすすめします。
契約書
複数の企業で交わす契約書については、その内容によって課税文書としての取り扱いが異なります。そこで以下では、経営者が特に押さえておきたい契約書に関して、どのような扱いになるのかを簡単にまとめました。
| 文書の種類 | 印紙税 |
|---|---|
| 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書) | 4,000円 |
| 信託行為に関する契約書(第12号文書) | 200円 |
| 債務の保証に関する契約書(第13号文書) | 200円 |
| 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書) | 200円 |
| 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書) | 200円(1万円未満は非課税) |
上記のなかでも「継続的取引の基本となる契約書」は、ビジネスシーンにおいて交わす機会の多い契約書です。売買取引基本契約書や代理店契約書など、契約期間が3ヵ月を超え、かつ更新の定めがあるものはすべて第7号文書に該当するため、収入印紙の貼付を忘れてはいけません。
ちなみに、フランチャイズ本部との間で交わす加盟店契約書は、基本的に第7号文書として取り扱われます。
約束手形または為替手形
第3号文書にあたる約束手形または為替手形は、記載された金額によって以下のように印紙税額が異なります。
| 記載された手形金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 10万円未満 | 非課税 |
| 10万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超~3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
ちなみに、金額の記載がない手形や、手形の複本・謄本は非課税として取り扱われます。また、基本的には「手形の金額を補充した人」が納税義務者となるので、こちらの点も合わせて覚えておきましょう。
その他の文書に関する情報は国税庁ホームページにて確認してみてください。
出典:国税庁ホームページ | 印紙税額の一覧表(第1~4号文書)
国税庁ホームページ | 印紙税額の一覧表(第5~20号文書)
収入印紙が不要なケースとは?
受取金額が5万円を超える場合であっても、印紙税がかからない形で取り引きをすれば、領収書に貼る収入印紙は不要となります。では、具体的にどのような取り引きが該当するのか、以下で詳しくご紹介していきましょう。
クレジットカードでの取り引き
クレジットカード決済をはじめ、現金のやり取りが直接発生しない信用取引は、印紙税の対象外になります。ただし、「クレジットカードによる決済」である旨を領収書に明記しない限り、非課税取引としては取り扱われません。
なお、電子マネー決済は信用取引には該当しないため、現金による取り引きと同じように収入印紙(印紙税)が必要になります。
電子データでの取り引き
FAXやPDFなど、電子データによる取り引きも印紙税の対象外です。つまり、領収書を電子化しておくと、取引金額が増えても収入印紙が不要となるので、社内の経費を大きく節約できるでしょう。
紙の領収書に比べて送付・管理の手間がかからない点も、電子データによる取り引きの大きなメリットです。
収入印紙の正しい割り印(消印)方法
収入印紙を文書に使用する際には、割り印(消印)を押す必要があります。最後に、この割り印が必要になる理由や、割り印の正しい押し方などをご紹介していきましょう。
収入印紙に割り印が必要な理由
切手のような見た目である収入印紙は、単に貼るだけでは再使用ができてしまいます。その点を防ぐために、印紙税法の第8条には「文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消さなければならない」と定められています。
つまり、収入印紙に割り印が必要な理由は”再使用の防止”です。割り印を正しく押せていないと、場合によっては脱税とみなされる恐れがあるので、以下で正しいルールをしっかりと身につけておきましょう。
割り印の正しい押し方
割り印は「収入印紙が使用済みであること」が判明すれば問題ないので、必ずしも文書と同じ印鑑を使用する必要はありません。正しいルールを守れていれば、シャチハタや日付印、ボールペンなども使用できます。
ただし、以下の点は確実に守る必要があるので、割り印を押す前にしっかりと確認をしておきましょう。
- 文書と収入印紙にまたがるように押す
- 鉛筆や消えるインクなど、簡単に消せるものは使用しない
- ボールペンで印をつけるときは署名をする
上記だけではやや分かりづらいので、以下では割り印のOK例とNG例を簡単にご紹介します。
| OK例 | NG例 |
|---|---|
| ・シャチハタや日付印を使う | ・ボールペンで線を引く |
| ・ボールペンで苗字を記載する | ・ボールペンで丸印を書く |
| ・屋号の入ったゴム印を使う | ・鉛筆で苗字を書く |
ちなみに、収入印紙の割り印は文書作成者以外でも押すことが可能です。つまり、代理人や従業員などが代わりに押しても問題ありませんが、誰が押す場合であっても上記のルールは守る必要があるので気をつけましょう。
割り印を間違ったときの対処法は?
割り印を間違った方法で押してしまった場合は、別の部分に正しい方法で割り印をすれば問題ありません。例えば、収入印紙の右側で割り印に失敗したときは、左側に正しい方法で割り印を押すようにしましょう。
なお、その文書を使用する見込みがない場合は、税務署に申し出ることで印紙税の還付を受けられます。
常に最新の情報をチェックし、正しいルールを身につけよう
収入印紙には正しい使用方法があり、貼付する文書によって納めるべき金額も変わってきます。一般的な企業では、さまざまなタイミングで収入印紙を貼ることが必要になるので、経営者を目指す方はこれを機に正しいルールを身につけておくことが重要です。
なお、印紙税が非課税になる範囲など、今後の法改正によってはルールが変わる可能性も考えられるため、収入印紙について調べる際には必ず最新の情報をチェックするようにしましょう。
公開日:2020年10月12日