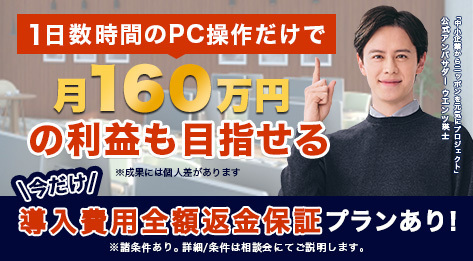脱サラしてうどん屋を開業!必要資金や準備を徹底解説
最終更新日:2024年09月20日

うどんは、手軽に食べられる国民食の一つとして親しまれています。脱サラしてうどん屋を開業する人が増えていますが、うどんの全国チェーン店が人気を集めるなかで繁盛店を目指すにはどのような準備が必要なのでしょうか。
今回はうどん屋の開業に必要なスキルや必要資金、メニューづくりから集客までの開業の流れ・繁盛店の目指し方を紹介します。
脱サラでうどん屋を始める人は意外と多い
2000年前半に讃岐うどん第4次ブームが巻き起こって以来、うどんの人気は堅調に推移しています。
うどん専門のチェーン店が全国展開され、手軽にうどんを食べられるようになったことも人気を後押ししています。うどん・そばの外食市場は、過去10年で1兆円規模と安定しているため、狙い目の市場と考えてうどん屋の経営を始める人が少なくありません。
手軽に食べられるうどんがファーストフードとして定着する一方で、価格が高くてもこだわりの味を楽しみたい客層も見られ、市場自体も多様化しています。味にこだわったうどんを提供しようと、脱サラしてうどん屋を個人で開業する人も意外と多いのです。
うどん屋になるために必要なスキル3選

うどん職人になるには修行が必要だとイメージしがちですが、飲食業界が未経験でも十分にチャレンジできます。しかし、うどん屋を開業して繁盛店に成長させるためには、経営に関する十分な知識が必要です。
うどん屋になるために必要なスキルを紹介します。
1.うどん調理のスキル
うどん屋を始めるには、最低でも麺をゆでて見栄え良く具を盛り付けるスキルが必要です。麺の太さや求める歯ごたえなどによっても、ゆで時間は微妙に変化します。具の下ごしらえや、温かいうどん・冷たいうどんごとのだし作りも必要です。だし作りでは、かつお・昆布などの素材や濃口・薄口といった醤油選びも重要になってきます。
ほとんどのうどん屋では揚げ物を提供しているため、基本的な天ぷらの揚げ方も身につけておく必要があります。うどん・そばを選べるようにしたり丼物などのサイドメニューを提供したりする場合は、提供メニューごとの調理スキルも必要です。
2.衛生管理の知識
うどん屋に限らず、飲食店を経営するには食品衛生責任者の資格が必要です。食品衛生責任者とは、食品を安全に提供できるよう常に店舗の衛生面を確認する役割で、店舗ごとに必ず配置が求められます。接客スペースや調理設備などの清掃・消毒状況の管理だけでなく、スタッフの体調管理も行います。
食品衛生責任者は1日で取れる資格なので、飲食業界が未経験でもスムーズに衛生管理の知識を身につけることが可能です。
なお、受講日程の関係で資格取得が間に合わない場合は、最寄りの保健所に相談すれば、資格取得前に営業を開始できる場合があります。
3.お店を経営するスキル
脱サラしてうどん屋を開業するには、何よりも経営知識が重要です。
調理や衛生管理のスキルは独学で身につけることができ、比較的難易度は低いと言われています。在職中に調理関係の専門学校に通い、開業に向けて技術を高めていくのも一つの方法でしょう。
しかし店舗経営のスキルが不十分だと、せっかくうどん屋を開業したとしても失敗に終わる恐れがあります。収益目標や原価率の設定はもちろん、集客の知識も必要です。うどん屋のオーナーとして求められる経営知識については、後ほど詳しく解説します。
開業前に考えたいうどん屋の方針

麺の品質は、うどん屋にとっての生命線です。自家製にするか製麺業者から仕入れるのかによって、店舗のコンセプトは大きく変わります。ターゲットにする客層を考えながら、うどん以外のメニューやトッピングの内容を検討することも繁盛店を目指すためには大切です。開業前に、麺とメニューの方針を徹底的に検討するようにしましょう。
うどんは自家製麺・仕入れ麺のどちらを使うか
うどん屋のコンセプトを考える前に、自家製麺にするか仕入れ麺を使うかを検討しましょう。
手打ちで麺をつくる場合、生地づくりから熟成・カットまで約6時間ほどかかります。ボウルや麺棒・テーブルがあれば麺を作れるため設備投資は必要ありませんが、粉の特性や季節によって麺の作り方に変化が生じるため、難易度は高くなりがちです。また、1日に提供できるうどんの量にも限りが出てきます。
店舗に製麺機を置く場合は麺づくりの労力が少なく済み、客数の変化に応じて製麺量を柔軟に調整できます。手打ちとひけめのない麺を作れる反面、初期投資は高額になりがちです。
また、仕入れ麺を使う場合は初期投資を少なくでき、麺の品質が安定しているのが店舗運営にとってはメリットです。しかし、客数の予測が外れると仕入れた麺が廃棄ロスになるため、立地や季節に応じて客数をシミュレーションした上で発注する必要があります。
うどん以外のメニューを出すかどうか
うどんに徹底的にこだわるのか、またはサイドメニューも充実させるのかも、うどん屋を開業する前に十分検討しておくことが大切です。提供するメニューによって、必要なスキルや設備も変わってきます。そばも提供する場合は、うどんの麺と同様にそばにも特徴を持たせる必要もあるでしょう。
うどん1本で勝負する場合、麺やだしにこだわり抜くことで繁盛店に成長できる可能性を秘めています。一方、年中同じメニューだと顧客から飽きられる懸念もあるため、季節に応じてメニューを変えるなどの工夫は必要です。
サイドメニューは天ぷらだけでなく、丼ものやおにぎり・いなり寿司など幅広く展開できます。定食として提供することで、客単価アップも期待できるかもしれません。一度にメニューの幅を広げすぎると材料の廃棄ロスのリスクが生じるため、曜日ごと・月ごとのローテーションでの提供を検討するのも一つの方法です。
脱サラしてうどん屋を開業する方法

うどん屋を開業するには調理技術や衛生管理の知識を身につけるだけでなく、店舗作りも欠かせません。設備投資や運転資金の確保、そして開業したうどん屋の魅力を伝えるための集客戦略も重要です。脱サラしてうどん屋を開業するまでの流れを解説します。
コンセプトやメニュー作り
うどん屋のコンセプトやメニューを決めるためには、開業しようとするエリアの特性を調査したり、うどんの専門店やチェーン店で提供しているメニューの傾向を分析することが大切です。前述したように、うどん1本で勝負するかサイドメニューを充実させるか、この段階で方向性を決めておきましょう。
価格を高めに設定してうどん自体へのこだわりを徹底する店舗や、ご飯もの・トッピングを充実させて幅広く顧客を獲得する店舗など、コンセプトはさまざまです。昼と夜でメニューを変えて高収益を目指す店舗も見られます。提供するメニューも、おいしさと顧客のニーズ・原価率のバランスを考えながら検討しましょう。
味の決め手となる粉を仕入れる
次に、うどんの味を決める小麦粉の仕入れ先を決めます。うどん専用の小麦粉は市販されていますが、麺の太さやだしの風味に合った麺をつくるために、独自の割合で小麦粉をブレンドするうどん屋も少なくありません。実際に作った麺を試食して、味に納得できた段階で、小麦粉の販売業者と売買契約を結ぶようにします。
仕入れ麺を使う場合は、既製品が店のコンセプトに合うかどうかを十分に確認することが大切です。オーダーメイドの製麺に対応してくれる業者もあります。また、小麦粉・仕入れ麺ともにサンプルを提供してくれる業者もあるので、有効に活用しましょう。
うどん屋の開業手段を選ぶ
うどん屋を開業する手段としては、主に脱サラ後に自分で店舗を持つ方法とフランチャイズに加盟する方法があります。
自分で店舗を持つ場合は、物件を決める前に開店するエリアや店舗物件のリサーチが必須です。飲食店の居抜き物件なら、調理器具や接客設備・什器類に関する投資を最小限にとどめられます。中古の什器を使うのに抵抗がない人なら、開業資金面でのハードルを下げるのに有効な選択肢です。
なかには、うどん専門店で何年か修行を積んでから開業する人もいます。のれん分けを受けられれば、修業先の評判を受け継ぎながら一定の集客も見込めるでしょう。
開業当初から繁盛店を目指したい人には、フランチャイズに加盟してうどん屋を開業するのも選択肢です。フランチャイズなら、本部から経営ノウハウやメニューなどの情報提供を受けられるだけでなく、調理方法や接客の研修も受けられます。開業後の経営支援も充実しているため、飲食業界が未経験の人でも安心です。
うどん屋に必要な開業資金を用意する
設備投資や運転資金の計画を立てることも、うどん屋の経営を続けるための大切なステップです。個人でうどん屋を開業する場合は、800万円前後の開業資金が目安となります。居抜き物件を借りれば費用を安く抑えられますが、物件によっては造作譲渡料の支払が発生する点に留意が必要です。
| かかる費用 | 金額 |
|---|---|
| 店舗を借りる場合 | 敷金・保証金、前家賃で最低100万円前後(都市部や立地条件の優れた場所は200~300万円目安) |
| 店舗の内装工事、調理器具・接客設備費 | 100~200万円 |
| 製麺機を購入する場合 | 200~300万円 |
脱サラで開業する場合、貯金や退職金を開業資金に充てる人が多いですが、金融機関から創業融資を受ける方法もあります。たとえば日本政策金融公庫では、飲食店などの生活衛生関係の事業を始める人向けに「生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)」を提供しています。
ほかの金融機関でも開業者向けの融資制度を提供している場合があるので、付き合いのある金融機関に資金調達について相談してみるのも良いでしょう。
物件や内装を決める
開業資金の目処がついたら、物件や内装を具体的に検討します。
うどん屋のコンセプトや売上目標に応じて物件の場所や広さを決めますが、初めて訪れる人でもわかりやすい場所で開業するのがおすすめです。郊外でうどん屋を開業する場合は、客席数に応じて駐車場を用意しておくと集客力が高まるでしょう。
内装も店舗のコンセプトに沿って、近隣の店舗と差別化を意識して決めていきます。純和風や和モダンなど店舗によって内装はさまざまですが、内装業者の提案を受けながら自分のセンスを織り込んでいくと良いでしょう。内装が来店客の印象に残れば、次回以降の来店につながるかもしれません。
必要機材・備品を揃える
内装を検討すると同時に、店舗を運営するための必要な機材や備品も揃えていきます。
業務用のゆで釜・ガスコンロや冷蔵庫などは店舗運営の効率化にも直結するため、調理場の広さや動線を考えながら使い勝手の良いものを選びましょう。揚げ物を提供する場合はフライヤーを用意すれば調理の安全性が高まるだけでなく、油の交換もスムーズです。テーブル・椅子や食器など接客に必要な備品も、店舗のコンセプトに合わせたデザイン・色彩のものを選ぶようにします。
キャッシュレス決済を導入する場合は、端末を提供している業者に問い合わせて加盟店審査を受けておく必要があります。加盟店審査には2~3ヵ月かかるため、開店に間に合わせたい場合は早めに手続きをとるようにしましょう。
うどん屋に必要な資格と届出を準備する
うどん屋に限らず、飲食店を開業する際は保健所に「飲食店営業の許可申請」が必要です。保健所によって許可条件が異なる場合があるため、物件の候補が決まった段階で最寄りの保健所に事前相談を行うのが一般的です。
許可申請が下りるまで約2~3週間かかり、店舗の立ち入り調査も実施されます。必要書類のなかに「食品衛生責任者」の資格者証も含まれているので、申請日までに講習を受講しておくようにしましょう。
なお、調理師免許がなくても飲食店の営業許可は申請できます。
集客や販売促進を検討する
うどん屋の開店日を決めたら、店舗の認知度を高める方法を具体化して集客につなげます。開店日の告知が早すぎると宣伝効果が薄れる可能性があるので、開店1週間前を目安に広告できるようにしましょう。
グルメサイトやフリーペーパーに広告を掲載する店舗が多いですが、最近ではInstagramやFacebookなどSNSを活用して集客を試みる店舗も増えています。来店客がうどんを食べる姿をイメージできるように、提供するメニューや店舗の外観・内装の写真を活用した宣伝をおすすめします。
うどん屋さんに失敗しないコツ
いざうどん屋さんを開業しようと思っても、失敗してしまうのではないかと不安な方も多いです。
そこでここではうどん屋さんになるべく失敗せず、成功しやすくなるコツを紹介します。
開業に失敗してしまった口コミを参考にする
こちらの動画では開業に失敗して1500万円の赤字となってしまった方の口コミインタビューが掲載されています。
実際にどのように失敗してしまったのか、失敗事例を見て自分はどのようにしたら良いか考えられると良いですね。
フランチャイズで成功している人の口コミを見る
こちらは実際にフランチャイズで6店舗も開業している古川さんの口コミインタビューです。
フランチャイズの出店で成功できるか不安な方は参考にしてみてください。
集客方法を考える
うどん屋さんの失敗によくあるのが「うまく集客できなかった」という事例です。
2023年に閉店したうどん屋さんを見てみると、人が来づらい田舎町のうどん屋さんがどんどん閉店しています。
費用をかけられるならなるべく人が来やすい立地を選ぶのが良いですが、予算的に厳しい場合は集客を効果的に行っていきましょう。
- SNSを積極的に投稿する
- ホームページを作る
- 近くのエリアにチラシを配る
- 駅にポスターを貼ってもらう
- お店の前に分かりやすい看板を作る
- チャレンジメニューを作る
など、上記の集客方法を試していくと良いでしょう。
SNSやホームページは、詳しい20代のスタッフに依頼してみるのも一手です。
繫盛店のうどん屋を目指して開業準備を進めよう

うどんの外食市場は安定しているため、店の独自性を追求していけば、脱サラしてうどん屋の開業に成功できる可能性はあります。
ファーストフードとしての地位が定着する一方で、価格が高くても麺やだしへのこだわりを求める顧客も少なくありません。
店舗の経営を長続きさせるには、チェーン店にはないコンセプトを明確にしたり、魅力的なメニューを打ち出したりすることが大切です。繁盛するうどん屋を目指して開業準備を進めていきましょう。
公開日:2023年01月31日