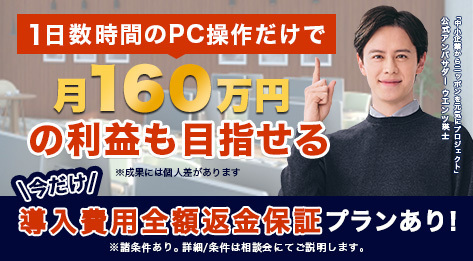家賃は経費にできる?個人事業主必見の家賃按分の方法や注意点
最終更新日:2024年09月20日

こちらでは、「自宅の家賃を経費にできるの?」という疑問を抱えている個人事業主に向けて、お役立ち情報をまとめています。
家賃を経費にするための「按分」の方法や、家賃以外で経費にできるもの、さらに按分する際の注意点などをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、経費をおさらい
経費とは事業を営む上で発生した費用全般を指し、経費にできる費用の主な例としては下記が挙げられます。
- 租税公課
- 消耗品
- 旅費交通費
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 荷造運賃
- 修繕費
- 減価償却費
- 利子割引料
- 新聞図書費
- 寄付金
- 雑費
租税公課のなかでも罰金は経費にできないなど一定のルールはありますが、事務作業で使うボールペンの購入代や出張時の交通費など、業務で発生した費用は基本的に経費に計上できます。
また、外部に外注する場合は外注工賃、従業員を雇う場合は従業員の給与や福利厚生費なども経費として計上可能です。
個人事業主の家賃は経費になる?
自宅で仕事している個人事業主は家賃を経費にできますが、家賃は事業用だけでなく、個人の生活のために支払っている費用でもあります。
経費にできるのは「事業を営む上で発生した費用」だけなので、まずは家賃を事業用と個人用に分ける「家賃按分」という作業をしなければいけません。
また、自宅以外に店舗や事業所を所有している方でも、自宅で作業する機会があったり、自宅を事業用の倉庫として使っていたりする場合は家賃按分して経費に計上可能です。
家賃按分の計算方法
こちらでは、家賃按分の計算方法を賃貸と持ち家それぞれのケースで紹介しています。
実際に、どのように家賃を按分するのか確認してみましょう。
賃貸の場合
自宅が賃貸の場合、自宅の「使用時間」または「使用面積」のどちらかを基準に家賃を按分するのが一般的です。
使用時間と使用面積どちらの按分方法を採用するかは、基本的に個人事業主が自分で決めて問題ありません。
下記では、使用時間と使用面積それぞれのパターンの按分方法を紹介しています。
<使用時間で按分するケース>
- 家賃は1ヵ月8万円
- 業務で自宅を使用している時間は1日8時間、1ヵ月の稼働日数は25日
1ヵ月720時間(24時間×30日)のうち、自宅を業務で使用している時間は200時間(8時間×25日)の約28%です。つまり、経費に計上できるのは家賃8万円の28%にあたる22,400円となります。
<使用面積で按分するケース>
- 家賃は1ヵ月8万円
- 自宅の面積は50㎡、業務で使用している面積は25㎡
業務で使用している面積は50㎡のうち25㎡の50%、経費に計上できるのは家賃8万円の50%にあたる4万円です。
持ち家の場合
一方、持ち家の場合は建物の「原価償却費」を基準に按分することが一般的です。
減価償却とは、住宅などの大きな買い物をしたときに、費用を一度に計上せず耐用年数(使用可能な期間)に合わせて分割して計上すること。
減価償却費は「建物の取得価額(※)×通常の耐用年数の償却率」で求めるのが一般的ですが、入居後しばらく経ってから事業を開始した場合は、まだ償却していない未償却残高を求めなければいけません。
<未償却残高の求め方>
未償却残高 = 建物の取得価額 -(建物の取得価額×0.9×耐用年数の償却率×経過年数)
上記の計算方法で算出した金額に、事業で使用している割合を乗じることで経費に計上できる家賃がいくらか分かります。
具体的な耐用年数や償却率は国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」や「減価償却資産の償却率表」から確認できますが、自身で計算すると間違いが発生しやすいため、確定申告ソフトなどで正確な金額を確認するのがおすすめです。
(※)…取得価額とは、物品を購入したときにかかった額のこと。
個人・事業用の区別が難しい場合はどうする?
家賃を按分するときは使用実態に則すことが重要ですが、どうしても事業用と個人用を区別できない場合は50%ずつ分けるという考え方があります。
特に自宅での仕事を本業としている方であれば、1日の半分が事業用だとしても不自然ではないでしょう。
ただし、1日の稼働時間が短い副業の方、自宅とは別に店舗や事務所を構えている方などは、自宅での滞在時間や睡眠時間などを含めると50%に達するとは考えにくいため注意してください。
家賃以外で経費にできるもの
住宅などの事業用と個人用の両方で使われるものに対する費用は「家事関連費」と呼ばれ、上述した家賃のように按分して経費に計上できます。
こちらでは、家賃以外で経費にできるのものを紹介しているので、該当するものがないかぜひ確認してみてください。
駐車場代
出張で使ったコインパーキング代や、事業用の車を駐車する月極駐車場の料金は経費にできます。
月極駐車場の料金については、車を事業用のみで使っているのであれば全額経費にできますが、個人用も兼ねている場合は使用実態に則して按分しなければいけません。
例えば車(事業用6割、個人用4割)を料金1万円の月極駐車場に駐車する場合、経費にできるのは6割の6,000円です。
ガソリン代などの車両関連費
ガソリン代や車検代などの車両関連費も経費にできますが、こちらも事業用と個人用の両方で使っている場合は按分する必要があります。
按分の計算方法としては、「使用日数」と「走行距離」を基準とすることが一般的です。
そのため業務で車を利用する際は、走行した日付や距離をメモしておくのが良いでしょう。
水道光熱費
まず光熱費の按分方法は、「コンセントの数」または「電気の使用時間」を用いることが多いです。
自宅にコンセントが10個あり、そのうちの3つを事業用で使っているのであれば、電気代の3割を経費にできる可能性があります。
水道料金やガス代は、使用した回数や時間を基準に按分するのが一般的です。
ですが、水やガスの使用実態を事業用と個人用に分けるのはかなり難しいため、これらの費用を経費にするのはあまり現実的ではないでしょう。
通信費
経費にできる通信費は、携帯電話や固定電話、インターネット回線、Wi-Fiなどの使用料金です。
例えば1台の携帯電話で1日5時間ずつ事業用と個人用でインターネットを利用しているのであれば、インターネットの通信料金を5割ずつ按分して経費にできます。
ただ、税務署から按分した割合の根拠を聞かれる可能性があるので、通話履歴など仕事の内容が分かる証拠を残しておくのがおすすめです。
家賃按分をするときの注意点
家賃按分は節税に効果的ですが、注意すべき点がいくつかあります。
こちらでは、家賃按分のポイントや条件などをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
家賃の全額を経費にしない
ここまで何度もお伝えしている通り、経費にできるのは事業で使用している分のみです。
事業用と個人用の境目が曖昧だからといって、家賃の全額を経費として申告するのはやめましょう。
個人事業主は、自身が按分した金額の根拠について聞かれたとき、他者が納得できるような客観性のある根拠に基づいて説明しなければいけません。
税務署から質問されても困らないよう、按分した割合の根拠となる資料を用意しておくことが大切です。
青色申告と白色申告では家賃按分の条件が異なる
事業用の割合が5割未満でも経費にできる青色申告に対して、白色申告で按分して経費にできるのは、事業用の割合が5割を超えているものが対象です。
つまり、たとえ自宅を事業用として使用していても、使用している時間や面積が5割に達していない場合は家賃を経費として計上できません。
人によっては白色申告を選ぶことで経費にできる対象がかなり減るため、節税対策を考えるのであれば青色申告のほうがお得だと言えるでしょう。
敷金は経費にできない
敷金は住宅を退去するときに返金される費用のため、たとえ自宅を事業用として使用していても按分することは認められていません。
退去時に敷金が差し引かれた場合は、そのときに修繕費などの項目で処理できます。
一方、礼金や不動産仲介手数料は、返金されない費用のため按分して経費計上が可能です。
これらの費用は自宅の使用実態に則して按分の割合が決まり、礼金に関しては20万円未満で地代家賃として経費計上、20万円以上で資産として処理します。
契約書などの保管が必要
確定申告で提出した内容に疑わしい点があると、税務署から指摘が入るリスクがあります。
家賃按分についても「なぜこの割合で按分したのか」と聞かれる確率が高いため、自宅の賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記したデータなどを必ず保管しましょう。
また、按分の計算方法を変えると不審に思われることがあるので、一度決めた方法を何度も変えないことがポイントです。
住宅ローン控除が利用できない場合も
持ち家の費用を按分した結果、事業用の割合が50%を超えると住宅ローン控除を受けられないため注意してください。
事業用の割合が50%未満の場合は、個人の生活で使用している分のみ住宅ローン控除を受けられます。
按分するより住宅ローン控除を選んだほうが節税効果が高いことは珍しくないので、どちらを選んだほうがお得か事前によく検討しましょう。
家賃按分のルールを覚えて賢く節税しよう
自宅を職場として使う方はもちろん、少しでも自宅で仕事をする機会がある方であれば、家賃按分は必ず覚えておきたい重要項目です。
どのような基準や計算方法で家賃按分して良いのか、そしてどのようなルールがあるのかなどを押さえ賢く節税しましょう。
公開日:2021年04月26日