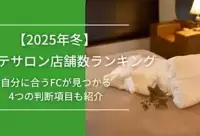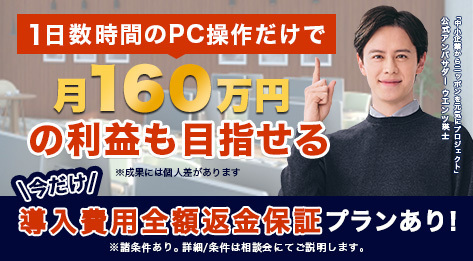独立開業を成功・失敗例から学ぼう!業種や開業資金別のメリット・デメリットとは
最終更新日:2023年02月27日

「脱サラして大きなビジネスチャンスにかけたい」もしくは「退職後に特技を生かして収入を得たい」などと独立開業を考えている方は少なくありません。
そこで参考となるように独立開業についてさまざまな視点から検証していきたいと思います。
独立開業とは?
誰もが一度は「独立開業してオーナーになる」という言葉に憧れるのではないでしょうか?ところが実際に独立開業してオーナーになり事業を展開していくのはなかなか大変なことです。また経営者となると収入面でもサラリーマンとは大きな違いがあります。
しかし独立開業して自らビジネスを展開している方からは、「やりがいが感じられサラリーマン時代とは比べものにならないほど充実している」という声も聞かれます。そこで独立開業について色々な側面から考えていきたいと思います。
独立開業することと、会社員でいることの違い
会社員として雇用されているのと、オーナーとしてビジネスを展開しているのでは色々な面で違いがあります。特に決定的に違いを感じるのは収入面になります。
会社員として勤務していれば毎月決まったお給料、そして会社の業績がよければボーナスが自動的に口座に入金されます。一定の期間勤めていれば昇級もありますし、働かなくてもその日の分のお給料がもらえる有給休暇というありがたい制度もあるので、「サラリーマン=安定した収入」と多くの人は感じるはずです。
しかし独立開業して自らがオーナーとなれば、安定した収入が約束されたサラリーマン時代とはうって変わり収入の保証はありません。雇用されていれば残業手当があり、アルバイトやパートであれば働いた分だけ収入が増えます。しかし経営者にはこの公式は当てはまりません。場合によってはサラリーマン時代よりもハードに働いているのに収入が少ない、もしくは赤字ということも十分あり得るのです。
ところがその反対のケースもあります。ビジネスが上手くいけばサラリーマンとして働いていた頃の数倍、または数十倍の収入を得ることも可能なのです。もちろんこれは独立開業のひとつの大きな魅力になっています。
会社員時代に培ってきた経験を生かして独立・開業できるFCを探す
独立と開業の違い
私たちは何気なく独立開業という言葉を口にします。しかしこの言葉の中には違う2つの意味が含まれています。
「独立」というのはそれまでに従事していた分野で新しくビジネスを始めることを意味しています。例をあげれば、美容師さんがそれまで勤務していたヘアサロンを辞め自分でお店をオープンさせる時にはこの「独立」という言葉があてはまります。
また「開業」という言葉は新しく事業を始めることを意味しています。つまりそれまで従事していた分野とは違う分野で起業する場合には、「独立開業」という表現はあてはまらないのです。
どんな業種で独立開業するか?
独立開業を目指す方がまず一番初めに決定しなくてはならないことは
「どのようなビジネスをどのようなスタイルで始めるか」ということです。
現在は産業も多様化してきてさまざまな業種が存在していますが、ここでは大きく【飲食業】【サービス業】【小売業】の3つの分野に分けて、独立開業する上でのそれぞれのメリットやデメリットについて紹介していきたいと思います。
飲食業で独立開業する
まずは起業を目指す方から人気の高い【飲食業】を取り上げてみます。
飲食店と言えばレストラン、居酒屋、カフェ、ラーメン屋などが頭の中に思い浮かぶのではないでしょうか。このような飲食業で独立開業を望む方は、
- 「長い間調理者として雇われていたが自分のお店を持ちたい」
- 「おしゃれなカフェを経営するのが夢だった」
- 「人が好きで人が集まる場所を演出したい」
など長年にわたりお店をオープンさせる夢を持っていた方が比較的多いようです。その他にも、
- 食べる・飲むと言う行為は私たちの生活の一部であり親近感も持ちやすい*
- 現在は「グルメ時代」で食への関心が高い
などの理由からも飲食業関係での起業は人気があるようです。
飲食業のFCブランドを探す
飲食業で独立開業するメリット・デメリット
さてここでは【飲食業】で独立開業するメリットとデメリットについて検証してみたいと思います。メリットとしてあげられるのは以下の2つの点です。
- 粗利益が高い
- 個性が出しやすく価格競争になりにくい
小売り業であれば仕入れ金額が販売金額の大部分を占めるので、数個売れただけでは利益は望めません。しかし飲食業であれば食事や飲み物の提供金額は仕入れ金額の数倍で設定可能なので粗利益が高くなります。
また、飲食業店はそれぞれの店の個性を出しやすいために、顧客の取り合いによる価格競争のリスクが他の分野に比べて少なくなっています。では次は飲食業を経営するデメリットをあげてみましょう。
- 休日、祝祭日に仕事で労働時間も長い
- 立地条件に大きく左右される
- 開業費用が高い
飲食業は営業時間以外にも仕入れ・下準備・清掃などやるべきことがたくさんあり労働時間は長くなりがちです。土日・休日・祝祭日と人が遊ぶ時に働かなくてはいけないので、小さいお子さんがいる方にはハードルが高い分野でもあります。
その他にもいくら美味しい食事や、良い雰囲気を提供できたとしても、立地条件が悪ければ集客は難しくなります。ところが立地条件の良い場所は物件費も高く、厨房設備や椅子・テーブルなどを揃えれば数千万円の開業資金が必要なケースもあります。
サービス業で独立開業する
次に【サービス業】を見てみましょう。サービス業は物ではなく「技術やサービス」を提供する業種で、弁護士事務所や税理士事務所、ヘアサロンやエステサロン、または託児所や学習塾、そして便利屋や修理屋など多種多様なものが存在しています。
とりわけ高齢化社会が到来した現在では、便利屋、ハウスキービング、介護関連など高齢者の生活をサポートする業種が将来性があると注目されているようです。また、少子化になり子供ひとりに高い教育費をかける親も増えてきたので、塾や幼児教室なども需要がある分野となっています。
このようにサービス業を展開するためには、顧客が求めているものを感じとり、的確に技術やサービスを提供することが非常に重要になります。
サービス業のFCブランドを探す
サービス業で独立開業するメリット・デメリット
ではこの【サービス業】で独立開業する場合のメリットとデメリットをあげてみましょう。メリットとしては、
- やりがい
- 無店舗でも起業が可能なものもある
- 仕入れや不良在庫などの問題が少ない
というようなことがあげられます。
サービス業は主として人を相手にするために、顧客から感謝されることがあり「やりがい」を感じられます。また業種によっては店舗をもたなくても運営できるものもあり、物件費用を抑えることもできるのがメリットです。
例えばハウスキービングなどのサービスは顧客の家に出向いて行うために、必要なのは小さな事務所だけです。また飲食業や小売り業と比べると仕入れの必要もほとんどないために、不良在庫のリスクも小さくなっています。デメリットとしては以下の3つがあげられます。
- 集客のために営業活動が
- 価格競争のリスク
- 技術やサービスの向上のための努力や資格取得
サービスは目に見えないものだからこそ内容や価格を宣伝して顧客の興味をひきつけなくてはなりません。また飲食店とは違い差別化が難しいこともあり、価格競争に陥るリスクも他の分野より大きいでしょう。
その他にも提供する技術やサービスの向上のために、講習参加や資格取得等の努力が必要なこともあります。
小売業で独立開業する
では【小売業】での独立開業についてみてみましょう。
小売業とは簡単に言えば物を販売するビジネスです。食料品販売、雑貨販売、衣料品販売などがよく知られたところです。
現在では大型スーパーやチェーン店が増え、八百屋さん、魚屋さん、もしくは靴屋さんと言った昔ながらの小売店は減ってきています。
しかしその反対にこれまでになかった個性的な小売店も出現してきました。例をあげると「子供ブランド服のリサイクル店」「海外輸入雑貨店」「カフェ併設のしゃれたフラワーショップ」「有機栽培の食料品専門店」などです。
また、現在では店舗を持たずネットショップで販売活動をするケースも多く、起業を思いついてから短期間で開業する人も増えています。
小売業のFCブランドを探す
小売業で独立開業するメリット・デメリット
さてこの【小売業】で独立開業する場合のメリットとデメリットはどうでしょうか?
メリットとしては以下のことがあげられます。
- ・自分の趣味関連や好きなものが扱える
- ・飲食業などに比べると労働時間が少ない
- ・ネットショップなら店舗不要・少ない資金で開業可能
さて【小売業】のデメリットといえばやはり
- ・粗利益が少ない
- ・仕入れが必要で在庫管理が難しい
- ・大手に参入されると経営が難しい
ということです。
一般的に仕入れ代金と販売代金の差額は少なく、飲食店に比べて粗利益が少ないので多量に販売しなければ利益が出にくくなっています。
サービス業と違い仕入れが必要で不良在庫などのリスクも大きくなります。また、大手は一度に大量の仕入れをして価格を抑えるので、個人店は価格競争に負けてしまいがちです。顧客としては同じ製品であれば当然安い方を選ぶからです。
独立開業で成功するために考えるべきこと
どんな業種で起業するのか決定して、いよいよ開業の準備。そうなったら熟考しなくてはならないのが【ビジネスプラン】です。
「とりあえずビジネスをスタートさせてからその場の状況に合せて先のことを決めて行く」
と言うように成り行き主義でビジネスプラン無しで成功した例は殆どありません。
もし独立開業を決意したのであれば、どのような方法でビジネスを展開していくかをじっくりと検討し計画を立て、その計画を順番に実行していくことが成功への第一歩になります。
独立開業後の集客プラン
ここでは独立開業のためにどのようにビジネスプランを立てるべきかを解説したいと思います。
「味が自慢の居酒屋」「きめ細かいサービスが自慢のハウスキービング」「海外からの一点ものアクセサリー」
このように趣味趣向をこらしたビジネスを始めてもお客さんが気づいてくれなければそこでビジネスは失敗となります。つまり、独立開業を目指した時に考えるべき重大な課題のひとつが「顧客をどのようにして集めるか」という【集客】プランの決定になります。
新聞の折り込み広告、ポスティング、ダイレクトメール、電話、ネット広告、ブログ、キャンペーン、イベントなど複数の集客方法が存在する現在では、ターゲットにする客層に対して効果的にアピールできる方法を選ぶことが大切です。
新聞の折り込み広告を使ってネイルサロンの宣伝をしても、興味を示す人の割合は少ないはずです。また高齢者を対象としたサービスをSNSやネット広告のみで宣伝しても、インターネットを使用する高齢者は少数なので効果的だとは言えません。この場合ではダイレクトメールや電話を使った宣伝の方が効果が期待できるはずです。
逆に若者が集まるような飲食店やコスメ・ファッショングッズなどは、ネットでの口コミ評価が大きな影響力を持っています。もちろん費用をかけず多くの人に宣伝したい場合にもSNSなどは活躍します。
ビジネスを始動させる前にはこのような点を考慮して、集客方法やその費用について詳しく検討するようにして下さい。
客単価を上げる
さて集客とともに大切なのが【収益】をアップするためのプランです。収益なしではビジネスを展開していくことは不可能になります。
では一体どうすれば収益をあげることができるのでしょうか?ここでは代表的な2つの方法を紹介したいと思います。
- 商品やサービスの単価を高くする
商品やサービスの単価を高く設定するためには、飲食店であれば高級食材や高級なお酒類の提供、サービス業であれば個別サービス、例えば塾の個別指導などサービスの内容のレベルアップが考えられます。また小売業ではブランド物や1点ものなどの取り扱いが考えられます。
- 顧客が1回に使う金額を上げる
顧客が1回に使う金額を引き上げるために使われる代表的な手法が、「まとめ買い」「セット価格」などです。「まとめて買うと◯パーセント引き」「1万円以上で◯◯プレゼント」などで誘導して、顧客が1回に使用してくれる金額をアップさせます。
リピーターを増やす
さて集客活動で集めた顧客を逃さずに【リピーター】にするためのプランも忘れずに考えて下さい。
特に競合相手が多い事業であれば、安定した収益を得るためのリピーター確保はビジネスの運命を左右する重要なポイントになります。リピーターを確保するために最も大切なのは「良い商品やサービスの提供」であることは間違いありません。商品やサービスに満足できなければ顧客は離れていきます。
しかしだからと言って「良い商品やサービス」だけでは顧客をひきつけておくことは難しいのが現状です。次々と起業してくるライバルがいるので、そのライバルの店、商品やサービスに顧客が流れていかないように積極的な働きかけや魅力的なアイディアが必要になります。
リピーター確保の代表的なものとしては、ポイントカード、会員制度、またはメルマガなどがあげられます。他にも定期的にイベントを開き顧客との距離感を短く保つという手法を使っているところもあります。
人材を育成する
もうひとつびビジネスを左右するものに人材があります。現在はひとりで事業を行っていても,将来経営が軌道にのりビジネス拡大ということも十分に考えられます。そうなれば当然人を雇うことになります。
そこでここでは〈人材確保・人材教育〉に焦点をあててみたいと思います。現在は人で不足と言われ、良い人材を確保するためには魅力的な労働条件と福利厚生を整えることが必要不可欠です。
人件費を抑えたいからと時給を低くすれば、良い人材は集まりにくくなります。どうしてもその仕事をしたいので時給は問題ではないという人も例外的にいるでしょうが、良い人材は他からも望まれるので時給の高い方へ流れてしまう傾向にあります。
またお給料の他に雇用される側にとって重要なのが福利厚生です。社会保険(厚生年金、健康保険)や社宅、保養所、フィトネススタジオ会員、などは仕事を探す側にとっては重要なポイントになります。学生などは食事提供があることに魅力を感じて応募してくる場合もあります。
次は、確保した人材をいかに教育するかです。
初めから完璧な人材などほとんど存在しません。しかし教育して素晴らしい人材にすることは可能です。すなわちある程度の時間とお金を投資して、自分の事業に必要な人材を育成することも経営者がすべき重要な課題になります。
良い人材を育てるためには、資格取得のバックアップ制度(補助金、試験の為の休暇,報償金制度)や、定期的に研修・講習に参加させるという方法があります。
仕入れ等、コストを見直す
独立開業にむけてビジネスプランを立てる上でもうひとつ忘れてはならないのが【コストの見直し】です。経費を抑えることができれば当然のこと利益は大きくなります。特に独立開業したての頃は売り上げを出すのが難しいために、経費を抑えて利益を大きくするように努力しなくてはなりません。
ではコストダウンを実現させるためにはどうすれば良いのでしょうか?飲食店などの場合は、多くの業者にあたり交渉することで仕入れ価格を下げることも可能です。またオフィスを構える必要があるビジネスの場合には、レンタルオフィスという選択肢があり、さらにシェアオフィスにすれば物件費は大幅にコストダウンさせられます。
そして人件費をコストダウンするために欠かせないのが、アルバイトやパートの勤務時間やシフトの見直しです。効率のよいシフトを組むためには「いつどれぐらいの労働力が必要か」というような業務内容の分析をきちんとして下さい。小さなコストダウンでも積もり積もれば大きなコストダウンになりますので、それぞれの経費をよく見直し利益アップにつなげましょう。
独立開業の失敗成功例
夢を実現して独立開業する人の全てが成功者になれるわけではありません。では誰が成功者となっているのでしょうか?成功した方の中には「単に運が良かっただけ」と語る人もいますが本当に運だけの問題なのでしょうか?その答えはNOです。
注意して独立開業の成功例と失敗例を分析してみると、どうして成功、もしくは失敗したのかが見えてきます。起業の結果を「運」だけで片付けてしまうのは正しくありません。実際に独立開業して成功した例と失敗した例を見て、その原因について説明していきたいと思います。
独立開業の成功例・パターン
では独立開業して成功した方の例を見てみましょう。ここで参考にするのは早期退職をして宅配のお弁当屋さんを始めて成功したAさんのケースです。
Aさんが開業したのは普通のお弁当屋さんではなく、あらかじめ注文をとり宅配をするというヘルシーが売りのお弁当屋さんでした。Aさんはもともと料理が趣味で、Aさんの奥さんも管理栄養士として働いていた経験がありました。
普通のお弁当屋さんであれば店舗が必要ですが、注文を受けて宅配するお弁当屋さんなので必要なのは調理場のみ。つまり物件費を大きく抑えることができました。
また注文を受け宅配するためムダのない仕入れが可能で、仕入れの失敗によるロスも殆どありません。
そしてヘルシーを売りにしたことで、一人暮らしや高齢者の夫婦、健康志向の方などがリピータとなり、開業してたった数ヶ月で安定した収入を得ることに成功しました。
気になる労働時間もランチをメインとした宅配弁当のために、調理と配達をあわせても1日に平均して6時間程度とサラリーマン時代よりも拘束時間が少なくなりました。
このようにAさんは
- 自分の得意としている分野を選んだ
- 物件費を抑えられた
- ムダのない仕入れができる注文宅配のシステム
- 時代のニーズに合う内容
で成功したのでした。
宅配弁当のFCブランドを見てみる
独立開業の失敗例・パターン

では今度は独立開業して失敗した例を見てみましょう。
調理師として働いていたBさん。親の遺産が入ったことを期に念願だった居酒屋をオープンしました。飲食店開店では設備をそのまま引き継ぐ「居抜き物件」を利用する人が多いなか、雰囲気作りにこだわったBさんは満足できる「居抜き物件」に出会えず、最初からの店作りをすることにしました。
凝った内装やバリ島からのインテリアで洒落たアジアン風居酒屋をオープンさせましたが、開業資金が不足し銀行から500万円を借り入れました。
開店当初は割引クーポンの配布と物珍しさも手伝いお客さんの入りもまあまあでした。しかし大通りから離れているために客足は減っていきました。Bさんは目立たなく隠れ家的な立地がうけると考えていましたが、この予想ははずれたのでした。
少ない売り上げから銀行への返済と家賃の支払い、人件費などを差し引くと自分の手元にはほとんどお金は残りませんでした。そんな状況から結局Bさんは店を閉め、チェーンの飲食店に再就職したのでした。
Bさんが失敗した理由は
- 物件や内装、設備費のかけすぎ
- ビジネスプランをしっかりと立てていなかった
- 立地条件の悪さ
という点にあります。
独立開業の成功、失敗を分けた要因
同じ食を扱うビジネスをスタートさせたAさんとBさん。
Aさんは健康ブームや高齢化社会という時代のニーズを考慮しながら業種を選択し、なおかつ仕入れが無駄になるリスクを軽減する〈お弁当の注文宅配〉というスタイルを選んで見事に成功しました。
Bさんは自分の理想の店にこだわり過ぎで多額の開業費用が必要になりました。また立地条件がいまひとつの場所に、集客・リピーター率・利益アップの対策をきちんとを立てないままで開業したことが敗因へとつながってしまいました。
この両者の例から分ることは、独立開業して成功するためには〈夢や理想の追求〉だけではなく、〈資金やビジネス展開のプラン〉という現実的なポイントを念頭において行動することがいかに重要かということになります。
独立開業の始めの一歩
では独立開業を決意した時にはどのようなことを準備すべきなのでしょうか?
ここでは独立開業のために考えるべきこと、またはすべきことを簡潔にまとめて説明していきます。
独立開業で何がやりたいかを見極める
独立開業を考える上でまず一番の柱になるのがビジネスの内容、つまり「何をするか」ということです。
独立企業を目指す方の中には「とにかく今の仕事に不満足だから」という方も少なくありません。しかし実際にビジネスを始めて成功しているのは「好きな仕事だった」もしくは「これが得意だった」という方が圧倒的に多くなっています。
好きなことや得意なことであれば当然知識も豊富ですし、もし独立開業して困難にぶち当たっても少々のことでは負けずに頑張れると言うメリットもあります。
つまりビジネスの内容を決定するときには〈儲けそうだから〉〈カッコイイから〉などだけではなく、自分の特性や可能性を冷静に見つめることが必要です。
独立開業に足りない知識・スキルを明らかにする
独立開業に資格が必要で、「好き」や「得意」というだけでは起業できないビジネスもあります。
たとえば飲食店を開業する場合には「料理が好き、または得意」というだけでは不十分です。かといって調理師免許が必要なわけではありません。絶対に持っていなくてはいけないのは「食品衛生責任者」という資格になります。これは講習に1日参加すれば取れる簡単な資格ですが、持っていなければお店は開けません。
さて資格には【国家資格】と【民間資格】があり、弁護士、税理士、医師、もしくは美容師などが保持しているのが国家資格で、開業のために必須の資格です。
民間資格には多種多様なものが存在していて、難易度はそれほど高くなくても起業するために役立つものがたくさんあります。例えば犬の美容師であるトリマー、ワインの専門家ソムリエなどは、ペットサロンやワインバーを開くためには持っておいて損のない資格です。
また資格なしで独立開業できるビジネスであっても、仕事で必要な【知識や技術】は身につけておくべきですので、開業までに間に合うようにスケジュールをたてて勉強するようにしましょう。
独立開業の計画を立てる
さて次は具体的に「開業前」「開業から軌道にのるまで」「経営が安定したら」という3つの時期に分けて、何をすべきかを解説していきます。
開業前にすべきこと
まず最も重要なのが開業資金の準備になります。自己資金でまかなえない場合には資金を調達しなくてはなりません。また業種によって役所の許認可が必要なものもあるので、必要な書類などを揃えて手続きを進めていきます。
きちんとしたビジネスプランを立てるのもこの時期にしておかなくてはならないことです。その他にも仕事に必要な知識やスキルの習得をするのもこの時期になります。
開業から軌道にのるまで
起業の目的はビジネスを始めることではなく、ビジネスを安定させそして拡大していくことです。そのためには宣伝や営業活動やビジネスプランの見直しが必要になります。
利益が少なければ人件費削減のためにアルバイトやパートを減らしたり、場合によってはビジネスのスタイルを変えたりして対応していきましょう。
経営が安定したら
経営が安定してきたら次に考えるのが将来への展望です。それまでは事業を安定させることが目的でしたが、次はビジネスを拡大するか、それともこのままの状態で続けるかということがテーマになります。この時期にはプライベート生活、資金、時代背景などを考慮しながら、その先のビジネスプランを立てていきましょう。
独立開業のための資金調達
さて独立開業に欠かせないのが開業資金です。自己資金ですべてカバーできるのであれば問題ありませんが、不足する場合には足りない分を何らかの方法で調達しなくてはなりません。
そこで是非知っておいてもらいたいのが「補助金」や「助成金」の制度です。
これらの制度は厚生労働省や経済産業省、ハローワーク、地方自治体などが行っている起業者を支援するシステムで、借入するのとは違い返済義務がないので起業者にとってはとても魅力的です。ちなみに補助金と助成金の違いは以下の通りです。
- 補助金 予算があり、条件が合っても受給が不可能なケースがある
- 助成金 条件さえ合えば受給可能
資金が足りないからと起業を諦めるのではなく、「どこからどれだけの資金を調達できるのか」をもう一度検討してみましょう。
独立開業の選択肢
起業するときには「ゼロから始める」「今までの分野での独立」、そして「フランチャイズに加盟して」と大きくわけると3つのスタイルがあります。
ここではその3つのパターンについて、それぞれメリットやデメリットを交えて紹介していきたいと思います。
ゼロからの独立開業
まずはゼロから始めて独立開業するパターンを見ていきます。
メリットは全く何も無い所から始めるために、自分の思い通りの個性あるビジネスが展開できることです。全てを自分で行うために大変ですが学ぶことも多くあります。
デメリットは全てをゼロから始めるので、莫大な準備期間と労力、場合によっては多くの開業資金が必要になることです。しかし成功した時に喜びが最も大きいのは、このパターンでの独立開業でしょう。
今までの経験を活かした独立開業
次は今まで経験したことのある分野で独立開業する場合です。
この場合のメリットは何と言っても既に技術や専門知識、または人脈を持ち合わせているということです。つまりゼロから起業よりも少ない時間と労力でビジネスをスタートさせるこが可能になります。0から新しい分野に挑戦するよりも、精神的・肉体的な負担が少ないと言えます。
デメリットは経験があるために固定観念に捕われ、新しいアイディアなどに欠けることでしょう。また以前の同僚や仲間がライバルになることもあります。
フランチャイズでの独立開業
最後はフランチャイズに加盟しての独立開業です。
最近ではフランチャイズも多様化してきてさまざまな業種や経営方法が存在しています。
さてフランチャイズに加盟しての起業メリットは大切なポイントを合理的に伝授してもらえることでしょう。またベースは既に用意されているので短い準備期間での開業が可能です。
研修やサポート制度があるところも多いのでイザという時に安心できて、知名度もあるために集客も比較的楽にできます。
デメリットはフランチャイズ加盟料金を支払わなくてはいけないことや、自分の理想のビジネス展開が難しい、または個性が少なくなるということです。
サポートが充実しているFCブランドを探す
独立開業を成功・失敗例で学ぼう!まとめ
独立開業することと会社員でいることの大きな違いは収入面です。会社員は安定して給料が入ってきますが、自らがオーナーとなれば、収入に保証はなくなり、失敗も成功も自分次第となります。
独立開業を目指す方は、まず初めに業界を決定しましょう。先程は、大まかな3つの分野として【飲食業】【サービス業】【小売業】のメリット・デメリットをご説明しました。
業界が決まったらビジネスプランを立てましょう。集客や売上のために、客単価・人材育成・コストなどについて考えていくことが必要です。成功するためには、理想だけではなく、現実にも目を向けて行動することが重要です。
ビジネスプランを立てたら、必要な資金を集めたり、スキルを身に着けたりするなどの準備に取り掛かります。
ゼロからの独立開業に不安のある方はフランチャイズ加盟を考えてみるなど、幅広い視野で進めていくと良いでしょう。
公開日:2022年05月20日