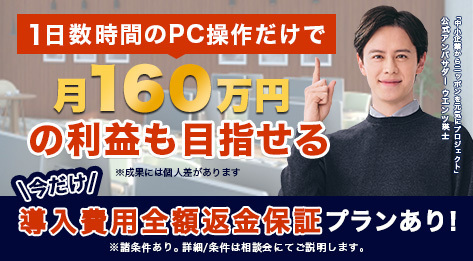副業の住民税はいくらかかる?計算方法や納付手順を解説
最終更新日:2024年09月20日

副業をしている人のなかには「収入は増やしたいがどのくらい税金が増えるか心配」という人もいるでしょう。副業収入は税金に影響するため、収入額ごとに目安の税額を知っておくと冷静に対処しやすいはずです。
この記事では、副業の住民税について、計算方法や収入額ごとの目安金額、納付の手順について詳しく解説します。所得税と住民税を混同している人も、この機会に違いを理解して正しく納税しましょう。
副業にかかる住民税とは?

副業にかかる住民税の基礎知識を見ていきましょう。混同しやすい所得税と住民税の違いについても詳しく解説します。
住民税は副業所得にかかる税金のこと
住民税は、正式には都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)の総称で、副業所得によって税額が決まります。地域のゴミ処理や上下水道、教育、 防災、公共施設といった事業に利用されています。
住民税の納税先は、当年の1月1日に住所がある市区町村です。年の途中で引っ越した場合、1月1日の時点に住民票があった市区町村に納税します。住民税では低所得者に対する非課税制度があり、各自治体が定めた条件に該当する場合は課税対象から除外されます。
東京都の場合は、以下の条件が設定されています。
- 生活保護を受けている方
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下
所得税との違い
副業に関する税金には、住民税と所得税の2種類があります。それぞれで管轄の行政機関や税額の算出方法が異なり、副業所得について申告が必要かどうかも変わるため、違いを正しく理解しておきましょう。
先述の通り、住民税が都道府県や市区町村に対して支払う「地方税」であるのに対し、所得税は国に対して支払う「国税」に分類されます。住民税の管轄は、各市区町村の役所が担っていますが、所得税は住民票のある住所の所轄税務署が担当します。
所得税の金額は課税所得に応じて異なる税率をかけて算出します。所得税は、所得額が20万円以下では確定申告が不要ですが、住民税については、前年の所得に応じた税金額を当年に支払います。当年の所得額に関わらず、住民税の納付が必要なので混同しないように注意しましょう。住民税の計算方法については後ほど詳しく解説します。
副業の住民税の納付手順
副業収入の住民税を納付するためには、所得の種類や金額に応じた対応が必要です。所得税と異なり、住民税は年間の所得額が20万円以下であっても自治体への報告義務があります。また、納付方法は2種類あり、本業への影響も考慮した上で選ぶことが大切です。住民税の納付手順を具体的に見ていきましょう。
副業の所得種類や金額を確認
まず、副業所得の種類や金額を確認します。ほとんどの副業は、次の3つの所得種類のいずれかに該当します。
- 給与所得:アルバイトやパートなど
- 雑所得:アフィリエイトや広告収入、フリマアプリやハンドメイド販売など
- 事業所得:事業としての継続的な収入
給与所得の場合は、本業と副業それぞれの源泉徴収票が必要です。給与所得以外の雑所得や事業所得では、本業の源泉徴収票、副業の経費を確認する領収書などを用意します。
副業の所得金額を上記書類で確認します。年間20万円を超えるかどうかで、確定申告を含む手続きの方法が変わります。
確定申告の申告期間は、翌年2月16日〜3月15日です。期間内に申告ができないと無申告加算税の対象となるため注意しましょう。源泉徴収票を受け取った後、年明けには必要書類を揃えて準備しておくとスムーズに申告手続きを完了できます。市区町村への申告も同様に3月ごろをめどに連絡しておきましょう。
所得が20万超なら所得税の確定申告を行う
副業の所得額が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。白色申告または青色申告が選べますが、控除額の大きい青色申告が使えるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかに該当する場合のみです。副業の所得が給与所得や雑所得の場合は、白色申告に限られます。
住民税とともに所得税も確定申告を通して算出され、税務署から市区町村の役所へ自動的に伝達されます。その後、市区町村で確定された住民税が本業の勤務先に通達されるかどうかは、納税方法により変わります。副業がバレたくない場合は、納付方法に注意が必要です。
所得が20万以下なら市区町村に申告する
副業所得額が年間20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市区町村へ所得額を別途申告する必要があります。当年の1月1日時点で住民票があった市区町村に対して、申告書類を提出します。
所得の申告は、担当窓口への持参の郵送のほか、インターネット上での電子申告が可能な地域もあります。いずれの方法でも、期日である同年3月15日までに行いましょう。
市区町村によって住民税申告書のフォーマットは異なります。各自治体の役所で配布しているほか、ホームページからのダウンロードや返信用封筒を使った郵送でも入手可能です。
申告書と併せて必要な書類として、主に下記があります。
- 所得の証明書類:給与収入の源泉徴収票、帳簿や領収書など(事業の場合)
- 各控除書類:社会保険料の領収書、医療費控除の明細書など
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
市区町村のホームページなどで必要書類や提出方法、期限を確認して準備しましょう。
特別徴収または普通徴収で納付する
住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があり、いずれかを自分で選択できます。それぞれで納付期限ややることが異なるため、理解した上で選ぶことが大切です。
勤務先に内緒で副業している場合、バレないためには「普通徴収」を選択します。ただし、普通徴収が選べないケースもあるので注意が必要です。
特別徴収
特別徴収とは、勤務先の企業が毎月の給与から住民税を天引きする納付方法です。自動的に給与から納税額が差し引かれるため、自分で手続きを行う必要がありません。一般的な住民税の納付方法で、正社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員といった他の雇用形態でも同様です。
特別徴収は、例年6月から翌年5月の間、12分割した金額が毎月の給与から天引きされます。確実に住民税を徴収できることから、国が推奨している方法です。納税者にとっては一括で支払うよりも負担が軽減されており、支払い忘れによる滞納リスクを避けられるというメリットがあります。
普通徴収
普通徴収は、納税者本人が納付書を使って納税する方法です。自治体が確定した税額や、納付期限などの情報が記載された納税通知書が手元に届くので、コンビニ支払いや口座引き落としなどの方法で支払います。
特別徴収では住民税額を会社が把握できるため、副業収入があると勘付かれる可能性が高まります。そこで普通徴収を選ぶことで、勤務先に副業を気づかれずに済むでしょう。
ただし、平成29年から東京都では事業主に特別徴収を義務化する動きを見せており、ほかの都道府県も追随しています。
また、副業がアルバイトやパートなどの給与所得の場合は、原則特別徴収となり、普通徴収にはできません。副業所得も本業と同様、特別徴収として給与から天引きされます。また、ふるさと納税や住宅ローン控除を利用している場合、副業分の住民税より減税額が大きいと、特別徴収から控除されるので注意しましょう。
普通徴収では、3ヵ月分の税額を1つの納付書で納めるため、一回あたりの負担額は特別徴収よりも大きくなります。また、納付し忘れによる滞納にも注意が必要です。
副業の住民税の計算方法

副業所得にかかる住民税の計算方法を簡単に説明します。住民税は下記の計算式で算出されています。
住民税=所得割+均等割+利子割+配当割+株式等譲渡所得割
多くの場合、所得割と均等割の2つの合計で税額が決まります。それぞれの金額は以下の通りです。
- 所得割:給与所得から所得控除を差し引いた金額×10%(県民税4%+市民税6%)
- 均等割:3,000~5,000円前後(都道府県・市区町村によって異なる)
均等割は副業をしていなくても、本業に対して発生します。所得割は、都道府県民税と市区町村民税の合計10%が副業所得にかかります。なお、利子割、配当割、株式等譲渡所得割は、特定の所得があった場合に加算されます。
副業にかかる住民税額の目安
ここからは、副業にかかる住民税額の目安を紹介していきます。副業の所得額ごとに、住民税のシミュレーションによって算出した一例をまとめましたので参考にしてください。
なお、実際に徴収される税額は個人で異なる可能性があります。各自治体のホームページや会計システムのWebサイトなどで公開されているシミュレーターを活用すれば、具体的な金額を計算できます。
※以降「Codeal副業確定申告シミュレーター」にて算出
※配偶者・子ども・70歳以上の老人なし
※社会保険や生命保険の特例や控除・医療費控除・ふるさと納税控除なし
所得20万円以下の場合
副業所得(雑所得)が20万円の場合、住民税の目安額は以下の通りです。
| 本業の年収(額面) | 住民税の目安 | 副業収入による増額分 |
|---|---|---|
| 200万円 | 75,100円 | 約+20,000円 |
| 300万円 | 124,500円 | 約+20,000円 |
| 400万円 | 180,200円 | 約+20,000円 |
| 500万円 | 244,200円 | 約+20,000円 |
住民税は、課税対象の所得額の約10%です。所得が20万円だと仮定すると1割の2万円前後が、副業分として増える計算です。
所得20万円超~50万円の場合
本業の所得が年間300万円で、副業所得(雑所得)が20万円超〜50万円の場合の住民税のシミュレーションを見てみましょう。
| 本業の年収(額面) | 副業の所得額 | 住民税の目安 | 副業収入による住民税の増額分 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 25万円 | 129,500円 | 約+20,000円 |
| 300万円 | 30万円 | 134,500円 | 約+30,000円 |
| 300万円 | 40万円 | 144,500円 | 約+40,000円 |
| 300万円 | 50万円 | 154,500円 | 約+50,000円 |
副業所得がない場合、住民税は約10万円ですが、副業により収入額の約1割が加算されていることがわかります。
所得50万円超の場合
副業所得(雑所得)が55万円の場合の住民税のシミュレーション結果です。
| 本業の年収(額面) | 住民税の目安 | 副業収入による住民税の増額分 |
|---|---|---|
| 200万円 | 110,100円 | 約+55,000円 |
| 300万円 | 159,500円 | 約+55,000円 |
| 400万円 | 215,200円 | 約+55,000円 |
| 500万円 | 279,200円 | 約+55,000円 |
副業の所得が80万円、100万円と増えても、約1割相当が住民税に加算される計算は変わりません。
副業の住民税も忘れずに申告をしよう
副業収入は、金額に関わらず住民税に影響します。確定申告の分かれ目となる所得額20万円と所得税が注目されがちですが、住民税の納付も重要です。所得額が20万円以下では、正確な税額を納付するために市区町村への申告を行いましょう。
住民税の金額は、所得額の約1割がおおよその目安です。正確な金額は所得控除額や、利子割などによって変わります。記事内で紹介した目安額を参考にして住民税の納付へ向けて準備しましょう。
公開日:2022年06月25日