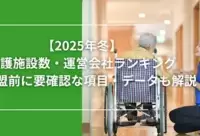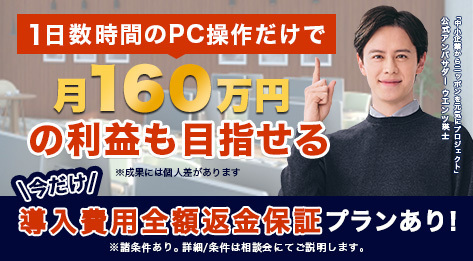租税公課とは?対象になるもの・ならないもの、具体的な仕訳例をご紹介!
最終更新日:2024年09月20日

租税公課には、税金や手数料などさまざまな費用が含まれます。
ただし、全ての費用を経費として落とせるわけではないため、経営者の方は費用別の正しい会計処理方法を理解することが大切です。
こちらでは、租税公課の対象と対象外の費用、計上時の注意点、仕訳例などを紹介しているので、計上方法に迷ったときはぜひ参考にしてみてください。
租税公課とは
租税公課とは、「租税」と「公課」を合わせた勘定項目です。
租税には国に納める「国税」と地方に納める「地方税」、公課には会費や組合費、証明書発行時の手数料など国や地方から課される公的負担金が含まれます。
租税公課には経費になるもの・ならないもの、経理処理方法によって異なるものなどがあり、正しく計上するためにはそれぞれの区分を理解しなければいけません。
また、酒税は納税申告書を提出した事業年度、自動車税は賦課決定(政府が納税額を決めた)のあった事業年度など、費用の種類によって計上時期が異なります。
そのため経営者の方は、どういった費用が経費になるのか理解するとともに、それぞれの費用の正しい計上時期を覚えることが大切です。
租税の対象になるもの
租税の対象になるものとしては、下記の費用が挙げられます。
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税・軽自動車税
- 軽油引取税
- 都市計画税
- 事業税
- 事業所税
- 印紙税
- 登録免許税
公課の対象になるもの
公課の対象になるものとしては、下記の費用が挙げられます。
- 各種手数料(印鑑証明書や納税証明書などを発行する際にかかる手数料)
- 会費や組合費(商工会や商店会などに支払う会費・組合費)
上記の通り、公課には国や地方から課せられる会費や組合費に加えて、証明書の発行手続きで発生する手数料などが含まれます。
租税公課の対象にならないもの
上記では租税公課として経費にできる費用を紹介しましたが、たとえ税金や公的負担金であっても経費として算入できない費用があります。
下記は租税公課の経費対象外となるため、経費として計上しないよう注意してください。
- 法人税・法人住民税
- 加算税・延滞税
- 罰金
- 法人税から控除する所得税・外国法人税
- 贈与税
法人税や法人住民税は会社の税引き前利益から支払う税金であり、経費に計上できません。
また、確定申告を適正に行わなかったときの加算税、期限までに税金を支払わなかったときの延滞税、交通違反で支払う罰金などのペナルティ費用も経費の対象外です。
そのほか、所得税や贈与税も対象外となるためよく覚えておきましょう。
消費税は経理処理の方法によって異なる
消費税の会計処理方法は「税込経理」と「税抜経理」の2つがあり、どちらを選ぶかによって租税公課として計上できるかどうかが決まります。
まず税込経理とは、売り上げや経費を税込み価格で計上する処理方法のことです。
こちらの方法を採用する場合は、消費税を租税公課として計上して問題ありません。
税込経理ではわざわざ売り上げと税金を分ける必要がないので、帳簿付けを楽にできる点がメリットです。
一方、税抜経理とは売り上げや経費を税抜き価格で計上する処理方法のことを指します。
こちらの方法を採用する場合は、消費税を租税公課として計上できないため注意してください。
税抜経理は税込経理と比べて帳簿付けが面倒ですが、売り上げのみの金額をすぐに把握できる点がメリットです。
租税公課外だが控除対象になる税金も
相続税は、租税公課に含まれませんが控除の対象となります。
相続税とは故人から遺産を引き継ぐ際にかかる税金を指し、生きている人から贈与を受ける「贈与税」とは異なるため注意が必要です。
相続税では、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などの控除を受けられます。
ただし、相続税の申告手続きに関わる税理士費用などは経費として落とせないので、計上方法を間違えないようにしてください。
租税公課に関する注意点
こちらでは、租税公課に関する注意点を2つ紹介します。
下記の2点は租税公課の計上で特に迷いやすいポイントなので、適切な会計処理を行うためにしっかりと確認しましょう。
未払いの租税公課の扱い
不動産取得税や自動車税、固定資産税などの税金は、賦課課税方式による租税です。
賦課課税とは政府が納税する金額を決定した後に納税者へ通知する方式のことで、この方式を採用する税金は、原則「賦課決定(政府が納税額を決めた)のあった事業年度」の計上が定められています。
ただし、固定資産税のような分割して納付する税金は、納付のタイミングが翌事業年度にずれ込むケースも珍しくありません。
その場合、計上タイミングは賦課決定のあった事業年度ではなく、翌事業年度で良いとされています。
予納の税金の扱い
予納とは、正確な納付額が確定する前に見込みで納付することです。
予納の例としては、法人税・法人住民税のほかに、預金利子や配当金を受け取るときの源泉所得税などが挙げられます。
予納金を会計処理する際は、租税公課ではなく「予納金」や「仮払金」などの勘定項目で計上するため間違えないようにしましょう。
租税公課の仕訳例
こちらでは、租税公課の仕訳例を3パターン紹介します。
固定資産税の分割や自動車税の按分の仕訳方法も解説しているので、分割や按分の会計処理をしなければいけない方はぜひ参考にしてみてください。
1.事業税の仕訳例
下記は、事業税の仕訳例です。
事業税は毎年8月と11月の2回に分けて納付する必要があり、こちらでは1回の納付額を3万円と想定して仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 3万円 | 現金 | 3万円 | 個人事業税 |
| 租税公課 | 3万円 | 現金 | 3万円 | 個人事業税 |
2.固定資産税の仕訳例
下記は、8万円の固定資産税を4回に分けて納付する場合の仕訳例です。
まず固定資産税を賦課決定日に仕訳する場合、借方にはこれから納付する8万円の固定資産税を「租税公課」として立て、貸方にはまだ支払いが済んでいないため「未払金」の勘定項目を立てます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 8万円 | 未払金 | 8万円 | 固定資産税 |
そして、実際に1回目の納付を済ませた後は、下記の通り支払い済み納付額である2万円を未払金から取り崩す形で計上して完了です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 未払金 | 2万円 | 現金 | 2万円 | 固定資産税 |
また賦課決定日ではなく納付日に仕訳する場合は、下記の通り租税公課の勘定科目を使って一度に計上して問題ありません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 2万円 | 現金 | 2万円 | 固定資産税 |
3.自動車税を事業用と私用で按分する場合
下記は、自動車税を事業用と私用で按分する場合の仕訳例です。
1週間のうち自動車を利用する時間が10時間として、経費として計上できるのは仕事で利用する6時間分のみです。
自動車税は6万円として想定し、事業用(60%)と私用(40%)の割合で按分します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 3.6万円 | 現金 | 6万円 | 自動車税 |
| 事業主貸 | 2.4万円 | 自動車税(按分) |
事業用として計上する金額分は「租税公課」、私用で経費に落とせない分は「事業主貸」の勘定項目で仕訳してください。
租税公課の対象と仕訳を覚えて会計処理に活かそう
経営者の方は、まず租税公課の対象になるもの・ならないものを確実に押さえ、その上で消費税の取り扱いや控除できる税金などの理解を深めましょう。
また、租税公課の仕訳には固定資産の分割や家事按分などいろいろなパターンがあるので、計上方法が分からなくなったときは本記事をぜひ参考にしてみてください。
公開日:2020年12月11日