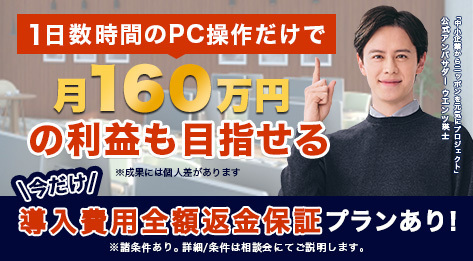葬儀屋のフランチャイズを始めるのに必要な準備
最終更新日:2024年09月20日

葬儀屋フランチャイズは、加盟する本部によって準備にかかる資金や手間が大きく変わるのが特徴です。
こちらでは、葬儀屋フランチャイズを開業する際に知っておきたい開業準備や本部選びのコツなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
葬儀屋フランチャイズの費用
はじめに、葬儀屋フランチャイズの開業・独立に必要な初期費用と運営資金を紹介します。
開業資金(初期費用)
葬儀屋フランチャイズを始めるために必要な開業資金(初期費用)は、200~7,100万円です。
主な開業資金としては、加盟金、保証金、葬儀場関連費、設備購入費、広告宣伝費、研修費などが挙げられます。
ただし、開業資金は開業方法によって大きく変わることに留意してください。
例えば自分で葬儀場を建設する場合、いくつかの本部では不動産の取得や建設にかかる費用を数千万~1億円超としています。
一方、葬儀場を建設せず借りるのであれば、葬儀場関連費は一切かかりません。
また、ペット専門の葬儀屋フランチャイズでは移動火葬車を利用することが多く、葬儀場を建てるより費用が格段に安いです。
葬儀屋フランチャイズの開業資金は上記で説明した葬儀場関連費が大半です。ただし、そのほかの加盟金や保証金、広告宣伝費、研修費なども本部やプランによって差があるため、それぞれ事前に確認しましょう。
運営資金
葬儀屋フランチャイズの運営資金は、1ヵ月で70~300万円です。
主な運営資金としては、人件費、Webシステム利用料、花の仕入れ費、設備のリース代、ロイヤリティなどが挙げられます。
これらの運営資金は葬儀の規模や本部の方針によって変わるため、あらかじめ本部の担当者へ費用の目安を確認するのがおすすめです。
例えば自社で従業員を育てることに力を入れている本部と、司会やセレモニースタッフをアウトソーシング(外部委託)で調達する本部では人件費のかかり方が異なるでしょう。
また、葬儀で使う設備を購入せずにリースでまかなう場合は、初期費用はかからないものの毎月のリース代を支払わなければいけません。
そのほかの費用としては、いくつかの本部では集客や顧客管理で使うWebシステムの利用料を5~10万円、ロイヤリティを売上高の3~5%に設定しているようです。
こちらの記事でも葬儀屋フランチャイズの開業資金(初期費用)や運営資金について詳しく解説しています。
葬儀屋フランチャイズの開業・運営に必要な資金について詳しく見る
葬儀屋フランチャイズの特徴
葬儀屋のような規模が大きい事業を始めるなら、手厚いサポートを受けられるフランチャイズへ加盟するのが安心です。
こちらでは、葬儀屋フランチャイズの具体的なサービス内容や、フランチャイズで事業を始めるメリット・デメリットなどを解説しています。
サービス内容
葬儀屋フランチャイズのサービス内容は、お客様の葬儀を手配し執り行うことです。
寝台車による遺体のお迎えや葬儀の打ち合わせ、葬儀当日の運営業務などが挙げられます。
これらの業務には多くの人員が必要なため、経営者だけで事業の運営はできません。
経営者は司会やセレモニースタッフ、事務員を育てたり、人手が足りない場合は専門の業者から人員をアウトソーシングしたりする必要があります。
また、上記は人間向けの葬儀の場合ですが、ペット専門葬儀の場合はここまで手間がかからず、経営者が火葬車でお客様のもとへ向かい一通りの作業を行うことがほとんどです。
メリット
葬儀屋フランチャイズを開業するメリットは、主に下記の3点です。
- 将来性があり安定した需要が見込める
- アウトソーシングで人件費を抑えやすい
- 希望に合った加盟プランを選べる
これらのメリットを理解し、どのように事業運営に活かせるか考えてみましょう。
■将来性があり安定した需要が見込める
高齢化が進む日本では死亡人口が増加しつつあり、2035~2040年頃には1年間の死亡者数が150万人を超えると推測されています。
このような時代的背景から、葬儀屋フランチャイズはしばらく安定した需要が見込めるビジネスだと言えるでしょう。
また、高額な費用をかけて派手な葬儀を挙げていた昔と違い、現在は「コンパクトな葬儀を挙げたい」や「費用を安く抑えたい」など、求められる葬儀の形が多様化しています。
葬儀屋フランチャイズでは本部の資金力を活かして多様な葬儀プランを用意できるため、個人経営よりもお客様のニーズに合ったプランを提案しやすいのが強みです。
■アウトソーシングで人件費を抑えやすい
葬儀には司会やセレモニースタッフ、花を準備するスタッフなど多くの人員が必要ですが、葬儀屋フランチャイズではアウトソーシングにより人件費を抑えられる可能性があります。
本部が適切なアウトソーシング先を紹介してくれるため、高額な費用の業者を間違って選んでしまう心配はありません。
開業したばかりで売り上げが少ない時期は社員を十分に雇う余裕がないことが多いため、アウトソーシングで費用を抑えられるのは大きな安心につながるでしょう。
また人件費だけでなく、葬儀屋フランチャイズでは本部から備品や消耗品を仕入れることで、仕入れ費を安く済ませやすいのもポイントです。
■希望に合った加盟プランを選べる
葬儀屋フランチャイズでは、経験や予算別に加盟プランを分けていることが多いです。
「同業種での経営経験がある方向けプラン」や「すでに物件を所有している方向けプラン」などと分かれているため、自身の経験や予算に合った方法で開業できます。
葬儀場を建てる場合は高額な費用が必要ですが、予算に余裕がない方は物件が不要なプランで開業するのが良いでしょう。
また、ペット用の葬儀屋フランチャイズであれば経営者だけで運営できる本部やプランもあるので、開業のハードルを下げたい方はぜひ検討してみてください。
デメリット
上記のメリットに対して、葬儀屋フランチャイズを開業するデメリットには「初期費用が高くなりやすい」や「立地選びが難しい」などのデメリットがあります。
■初期費用が高くなりやすい
葬儀屋フランチャイズは、加盟する本部や開業プラン次第では初期費用が高くなります。
特に葬儀場を自分で建設する場合は数千万円~1億円超の出費が見込まれるため、土地や不動産を所有していない方にとってはあまり現実的ではありません。
さらに加盟金や保証金、研修費などの費用がトータルで数百万円かかることを考えると、まとまった資金がなければ加盟は難しいと言えます。
葬儀屋フランチャイズの初期費用を抑えるためには、葬儀場をレンタルしたり設備をリースしたりなど、購入せずに環境を整える方法を考えることがポイントです。
また、葬儀の種類にこだわりがなければ、初期費用が安く済むペット葬儀を視野にいれるのも選択肢の一つでしょう。
■立地選びが難しい
葬儀場はそれなりの広さが必要なこと、そして人の死を扱うため事前に近隣住民の理解を得なければいけないことなどから立地選びが難しいです。
葬儀場が近くにあることに抵抗感を覚える住民は珍しくなく、さらに周辺に病院がある場合などは反感を買う可能性もあります。
ただ、葬儀屋フランチャイズは立地選びが難しいものの、本部の担当者がサポートしてくれるため過度に心配する必要はありません。
予算内で好立地に出店したいのであれば、いくつかの本部に相談した上で、提案内容が最も魅力的な本部を選ぶのがおすすめです。
成功・失敗のポイント
葬儀屋フランチャイズを軌道に乗せるためには、綿密な資金繰り計画や業界研究などさまざまな点を意識しなければいけません。
こちらでは、葬儀屋フランチャイズを成功させるために重要な3つのポイントを紹介します。
■予算に見合った開業方法を選ぶ
葬儀屋フランチャイズを始めるときは、必ず予算に見合った開業方法を選んでください。
特に葬儀業は売り上げが安定するまでに時間がかかる傾向にあるため、初期費用で無理をせず運営資金に余裕を持たせることが重要です。
予算に余裕がないのであれば無理に葬儀場を建設する必要はないので、物件を所有しなくても開業できる本部や開業プランを選びましょう。
どうしても自身の葬儀場を持ちたいのであれば、家族葬向けなどの小さな葬儀場が良いです。
例えば葬儀屋フランチャイズ「ティア」の収支一例によると、通常の葬儀場と家族葬用のコンパクトな葬儀場では初期費用が1億円近く変わるようです。
■トレンドに事業の方向性を合わせる
昔の葬儀はとにかく費用をかけて豪華な式を行うことが主流でしたが、最近では少し事情が変わりつつあります。
高齢化の影響で参列者にも高齢者が多く、体力的な問題から「短時間でコンパクトに式を挙げたい」という声も少なくありません。
また、葬儀にあまり費用をかけたくないお客様や、コロナ禍で少人数の式を行いたいお客様などもおり、葬儀に求められる形が多様化しつつあります。
葬儀屋フランチャイズを成功させるためには、上記のような葬儀のトレンドを理解し、事業の内容や方向性を合わせることがポイントです。
そのためには日頃からお客様の要望や業界研究を怠らず、葬儀業界の流れを把握する努力が求められます。
■地域の人との関係を大切にする
葬儀はめったに開催されない貴重なイベントであること、そして数十万~数百万円かかることから、お客様は「信頼できる葬儀屋に依頼したい」と考えていることがほとんどです。
葬儀屋フランチャイズは実績があるためすでに周囲から信頼されていることが多いですが、それでも日頃から地域の人々と良好な関係を構築することは大切。
地域住民をターゲットにするのであれば、親近感を持ってもらうために対面で会話できるイベントを実施するのも効果的でしょう。
例えば葬儀屋フランチャイズのなかには、チラシや公式サイトなどの広告宣伝のほかに、定期的なイベントを開いて対面で地域の人々とコミュニケーションをとる本部もあるので、各本部がどのような集客方法を行っているのか調べておくことをおすすめします。
葬儀屋フランチャイズを始めるときの準備
こちらでは、葬儀屋フランチャイズの開業準備を広告宣伝・広告宣伝・研修の3つに分けてまとめています。
開業準備の期間や流れは本部によって異なりますが、まずは大まかな流れを把握しましょう。
葬儀場
自分で葬儀場を持つ場合は、不動産の取得や建物の建設などの準備が必要です。
出店エリアの市場調査や葬儀場の設計、着工などを含めると1年を超えることも珍しくないため、ある程度の期間がかかることを見越して計画を立てましょう。
葬儀場の建設が完了した後は、音響や照明の設備、冷房、家具、カーテン、祭壇などの葬儀に必要な設備や備品類を揃えます。
ただ、これらの費用を全て自前で揃えると1,000万円を超えることもあるため、必要に応じてリースによる調達を検討してみてください。
広告宣伝
葬儀場のオープン前に、お客様へ自社のサービスを宣伝します。
広告宣伝の方法は本部によってさまざまですが、公式サイトの運営やチラシの配布、地域ポータブルサイトへの登録などが一般的です。
また、葬儀屋フランチャイズのなかにはオープンイベントや定期イベントなどを開催し、地域での認知度向上を目指す本部もあります。
特に最近は終活ブームもあり葬儀に興味がある方が増えているので、終活セミナーや葬儀相談会を開くのも良いでしょう。
研修
本部による研修を開業前に受けることで、葬儀の知識や作法、適した立ち振る舞いなどを身につけられます。
例えば葬儀屋フランチャイズの「ティア」では「ティアアカデミー」と呼ばれる独自の教育機関を設け、葬儀をとりまとめるセレモニーディレクターの育成を行っているのが特徴です。
「ティアアカデミー」の研修期間は3ヵ月間ですが、研修期間は本部によって異なるためよく確認しましょう。
また、人材が足りずアウトソーシングする場合は、本部が信頼できるアウトソーシング先を紹介してくれることが多いです。
葬儀屋フランチャイズ本部選びのポイント
葬儀屋フランチャイズの本部選びで重要なポイントとして、大きく以下の3つが挙げられます。
- 予算に無理のない範囲で開業できるか
- サポート内容は十分か
- 他社に負けない強みがあるか
葬儀屋フランチャイズは売り上げが安定するまでに時間がかかるため、予算に無理のない範囲で開業できる本部を選ぶ必要があります。
また、未経験で開業する方は、サポート内容が充実している本部を選ぶのがおすすめです。
特に市場調査や物件の準備は専門知識が必要なため、プロによる手厚いサポートが用意されている本部が良いでしょう。
そのほか、競合フランチャイズ本部にはない強みがあるかどうかも、その本部の将来性を判断するためにチェックしたいポイントです。
おすすめのフランチャイズ
葬儀会館ティア
『葬儀会館ティア』は、未経験者向けのきめ細やかなサポートが用意されているフランチャイズ本部です。
葬儀ビジネスに最適な立地選定や利便性に富んだ葬儀場のレイアウト考案、信頼できる人材アウトソーシング先の斡旋など、葬儀業界未経験者がつまずきやすいポイントを本部が徹底サポートします。
地域での認知度を向上させるドミナント戦略や、定期的なイベントを通した自社サービスのアピールなど、集客に力を入れている点も特徴です。
自社の教育機関「ティアアカデミー」では葬儀業について丁寧に教育してもらえるため、葬儀業界に精通していない方でも安心して開業を目指せるでしょう。
そうそうの森
株式会社フューネの運営する『そうそうの森』は、愛知県を中心に展開するフランチャイズ本部です。
創業から40年間にわたり安定した経営を続ける秘訣や、年間600件もの葬儀依頼を獲得する経営ノウハウなどを学びながら開業を目指せます。
また、開業パッケージは新規事業者向け・同時業者向け・同事業熟練者向けの3つに分かれており、自分のレベルに合った開業方法を選べるのがうれしいポイントです。
「失敗のない葬儀経営」を目指しているフューネでは、経営を経験したことがない方でも安定感のある事業運営をできるはずです。
ペットの訪問火葬 天国への扉
『ペットの訪問火葬 天国への扉』は、開業資金を抑えながらペット専門の葬儀屋フランチャイズを始めたい方にぴったりの本部です。
店舗を持つ必要がなく、火葬車をリースで済ませられる
のに加えて、経営者だけで運営できるため人件費もかかりません。
また、『ペットの訪問火葬 天国への扉』は全国に17店舗展開していますが、エリア制を採用しているため加盟店同士で争う必要がない点も安心できるポイントです。
開業前には手厚い研修が用意されており、今まで同業界で働いた経験がない方でも確かな知識をつけた上で開業できます。
公開日:2021年04月13日