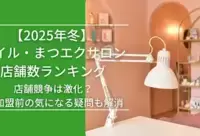個人事業主の節税対策!上手に税金を減らしてお金を残す方法とは?
最終更新日:2020年12月17日

個人事業主の方は、確定申告から納付まで全て自分で済ませなければいけません。
そのため節税の知識が足りなければ、不要な税金の支払いで損をしてしまう可能性があります。
そこでこちらでは、個人事業主が知っておきたい節税対策についてまとめました。
経費や控除に関する具体的な方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
個人事業主が支払う税金
個人事業主として働いている方は、自身が支払う税金について理解する必要があります。
会社員のように経理担当者が手続きしてくれるわけではないので、どういった種類の税金を納付しなければいけないのか把握しておくようにしましょう。
こちらでは、個人事業主が支払うべき4つの税金を紹介します。
所得税
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ所得に課せられる税金のことです。
「所得」とは1年間の売り上げから経費などの支出を差し引いた額であり、決して「売り上げ金額=所得」となるわけではないため注意してください。
具体的な所得税の金額は、所得から各種所得控除を差し引いた金額に課税して算出します。
個人事業主は翌年の確定申告期間(※)までに所得税の計算を済ませ、確定申告の内容に問題がなければ期限までに忘れず納付するようにしましょう。
(※)…例年は2月16日~3月15日ですが、前後する年もあります
消費税
消費税は事業年度の売り上げが1,000万円以上の個人事業主にのみ課される税金であり、下記の場合は納付が不要です。
- 事業年度の売り上げが1,000万円未満
- 開業から2年以上経っており、前々年の課税売上高が1,000万円未満
1,000万円を超える個人事業主の消費税納付額は、預かった消費税(事業の売り上げにかかる消費税)から支払った消費税(経費などにかかる消費税)を差し引いて求められます。
消費税の納付時期は3月となっているので、忘れず納付するようにしましょう。
住民税
住民税は、会社や事務所がある地方公共団体へ納める税金です。
住民税には「市区町村民税」と「都道府県民税」の2種類があり、所得に応じて納付額が決められるため個人事業主側が何か計算や申告をする必要はありません。
毎年6月に納付書が送られてくるため、分割または一括で支払うようにしてください。
事業税
事業税とは、法人または個人が運営する事業に対して地方が課す税金のことです。
法人の場合は「法人事業税」、個人の場合は「個人事業税」を都道府県など各地方自治体へ納付する必要があります。
ただし、事業税を支払う必要があるのは地方税法で定められた70の法定業種のみであり、さらに事業所得が290万円を超えない個人事業主の場合は納税義務がありません。
納付額は所得税を元に算出されるため個人事業主が計算する必要はありませんが、確定申告までに「自身が事業税の納付対象となるかどうか」について確認しておくのが良いでしょう。
納付対象となる場合は、8月と11月の2期にわたり支払いを済ませる必要があります。
個人事業主の節税対策
税金を自分で申告・納付しなければいけない個人事業主にとって、節税対策は事業を運営する上で重要な項目です。
こちらでは、個人事業主ができる節税対策の方法を6つ紹介するので、少しでも支払う税金の額を減らしたい方はぜひ参考にしてみてください。
経費を見直す
個人事業主の節税対策としてまず挙げられるのは、経費を見直すことです。
こちらでは、経費にできる税金と経費にできない税金を紹介します。
「経費として落とせる税金を今まで見逃していた」という方は、内容をしっかりと確認し次回の確定申告から活かすようにしましょう。
経費にできる税金
経費にできる税金の例としては、下記が挙げられます。
- 事業税
- 消費税
- 自動車税
- 自動車取得税
- 固定資産税
- 印紙税
- 不動産所得税
- 登録免許税
上記の税金のうち、事業に関わるものは経費として落とすことが可能です。
事業用で自動車を使用したり、所有物件を事務所として活用したりしている場合は忘れず計上するようにしましょう。
ただ、自動車や物件を事業用だけでなく私用でも使っている場合は、事業用と私用で按分する必要があるため注意してください。
また、上記の税金を計上するときは「租税公課」という勘定項目が使えるので、こちらも合わせて覚えおくことをおすすめします。
租税公課とは?対象になるもの・ならないもの、具体的な仕訳例をご紹介!
経費にできない税金
経費にできない税金の例としては、下記が挙げられます。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 加算税
- 延滞税
- 罰金
「加算税」とは申告を適正に行わなかったときに課される税金で、「延滞税」とは法定納付期限までに税金を支払わなかったときに課される税金です。
この2つの税金のようなペナルティで発生する費用は、たとえ事業に関連するものであっても経費として落とせません。
また、同様に交通違反をした際の罰金なども経費として落とせないため、よく覚えておくようにしましょう。
控除を見直す
所得税の節税には、経費のほかに控除を見直すのもおすすめです。
控除とは所得から差し引ける費用のことで、「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。
下記には控除の例を挙げているので、当てはまるものがないかぜひ確認してみてください。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 小規模企業共済掛金控除
- 医療費控除
- 専従者控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- 扶養控除
- 地震保険料控除
- 雑損控除
- 障害者控除
保険料の支払いや病院にかかったときの医療費、家族への給与などは控除の対象となるため確認しておくようにしましょう。
ただし、控除の上限額や控除できる対象者は所得額や申告方法(青色か白色か)で変わるため、まずは自身が当てはまるかどうか調べることが大切です。
青色申告をする
節税を考えるのであれば、白色ではなく青色で確定申告するのがおすすめです。
白色申告では最大10万円しか控除を受けられませんが、青色申告では最大65万円(※)の控除を受けられます。
また、家族と一緒に事業を運営している場合、白色申告では一定の金額(配偶者が86万円、それ以外の親族が50万円)を控除として差し引けるのみですが、青色申告では家族への給与を全額経費として落とせます。
そのほかにも事業が赤字だった場合は純損失を翌年から3年間にわたり繰り越せるなど、青色申告では白色申告にはないメリットが多くあります。
(※)…2020年より、e-Taxまたは電子帳簿保存での申告で最大65万円の控除を受けることが可能
減価償却の特例を活用する
青色で確定申告する場合、「少額減価償却資産の特例」を活用できる可能性があります。
パソコンやエアコンなど10万円以上の固定資産を購入した場合、通常であれば耐用年数に合わせ数年かけて償却しなければいけません。
固定資産を一括で購入した場合であっても、経費として全額を一度に落とせないのが一般的な減価償却です。
しかし、少額減価償却資産の特例を活用すれば、10万円以上30万円未満の固定資産を一度に経費として落とせます。
青色申告で確定申告をするのであれば、各種控除に加えて少額減価償却資産の特例も活用するのが良いでしょう。
短期前払費用の特例を活用する
個人事業主が何らかの費用を前払いした際、その支払った費用に関するサービスを1年以内に受ける場合は「短期前払費用」として経費に計上できます。
例えば、事業に使う機材のリース代(12ヵ月分)を一括で前払いしたとします。
この前払い費用は翌期で使う機材の費用を先に払っただけであり、本来であれば経費として落とせるのは翌期になってからです。
しかし短期前払費用の規定では、ある一定の条件(支払日から1年以内にサービスの提供を受けること、すでに料金を支払っていることなど)を満たしていれば、翌期ではなく当期の経費として計上して良いとされてます。
短期前払費用として認められるためにはいくつか条件があるので。どういった条件があるのかまずは調べてみるようにしましょう。
事業を法人化する
売り上げが大きい個人事業主は、事業を法人化するのも節税に効果的です。
まず個人事業主では、所得税が「累進課税方式」で徴収されるため、売り上げが大きい場合は最大45%の税率が課せられます。
一方、法人では「法人税率」が適用され、最大で課せられる税率は23.2%です。
そのため売り上げが大きく所得税が負担になっているのであれば、法人化したほうが納める税金の額を少なくできるでしょう。
そのほかにも、法人化することで経費にできる対象の範囲が広がったり、消費税の納付を2年間免税できたりといったメリットを得られます。
現金支出を伴う・伴わない節税がある
現金支出を伴う節税の例として、交通費や交際費、消耗品購入代などが挙げられます。
確かにこれらの費用を多く使えば経費が増えるため節税効果は得られますが、不要な支出を増やしてしまえば預金が減り経営を圧迫してしまいかねません。
一方、現金支出を伴わない節税には、白色申告から青色申告へ変えたり、償却資産や短期前払費用の特例を活用したりといった方法が挙げられます。
これらの方法であれば、手元のお金を減らさず節税することが可能です。
節税の知識をつけて賢く税金を減らそう
経費や控除の見直しに加えて、減価償却や短期前払費用の特例など節税対策にはさまざまな方法があるので、まずはどういった制度が使えるのか調べてみるようにしましょう。
「今まであまり節税について考えてこなかった」という個人事業主の方は、ぜひ今回の記事を参考に節税対策を始めてみてください。
公開日:2020年12月11日