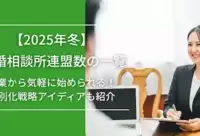消費税の仕組み理解できてる?納税義務者から納税額の計算方法までまとめて紹介!
最終更新日:2021年05月25日

消費税は、私たちの日常生活において一番身近な税金です。
消費者としては購入した商品やサービスにかかる消費税を支払うだけですが、事業者においては納税のための計算や申告などが発生するため、税率以外の知識も身につけておく必要があります。
そこで今回は、消費税の仕組みや計算方法、申告方法などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも消費税とは?
まずは、消費税のおさらいをしましょう。
消費税とは、商品や製品、サービスの販売・提供などに対して課税される税金のこと。
2021年4月時点での税率は以下の通りです。
| 税率名 | 税率 | 税率内訳(消費税率) | 税率内訳(地方消費税率) |
|---|---|---|---|
| 標準税率 | 10% | 7.8% | 2.2% |
| 軽減税率 | 8% | 6.24% | 1.76% |
参照:国税庁ホームページ
税金には、納税者が直接納める「直接税(※)」と事業者などの納税義務者を通じて納める「間接税」があり、消費税は「間接税」に該当します。
(※)…直接税の例:所得税、法人税、相続税、住民税など
消費税の仕組み
事業者が販売する商品やサービスの代金に上乗せされる消費税ですが、製造業者をはじめ、卸売業者、小売業者、消費者という流れで転嫁され、最終的に商品の消費やサービスの提供を受ける消費者が負担するという仕組みになっています。
こちらでは、消費税の仕組みを理解するうえで重要な2つのポイントを紹介します。
消費税の負担者と納税義務者は異なる
消費税は、消費者が商品やサービスの代金と一緒に支払うため、消費者に納税義務があると思われがちですが、実際は消費税の負担者と納税義務者は以下のように異なります。
- 消費税の負担者…消費者
- 消費税の納税義務者…事業者
このように、事業者には消費者から預かった消費税を代わりにまとめて税務署に納付するという役割があることを覚えておきましょう。
二重三重で課税されることはない
消費税は消費に対して課税される税金のため、製造や卸、小売などの取引段階で二重三重に課税されることがないような仕組みになっています。
例えば、販売店が製造業者から1,100円(税込)で商品を仕入れて3,300円(税込)で販売したとしましょう。
消費者が負担した消費税は300円となりますが、この全額を販売店が納税するのではなく、販売店が仕入れ時に負担した消費税100円を差し引いた【200円】を販売店が納税、卸の際に発生した消費税【100円】を製造業者が納税します。
このように、商品やサービスの売上から仕入れにおける消費税額を控除することで、税が累積しないような仕組みがとられているのも大きな特徴です。
消費税の課税対象・対象外について
では、どのようなものに消費税が課税されるのでしょうか。
こちらでは、消費税の課税対象・対象外のものについて紹介します。
消費税の課税対象のもの
消費税の課税対象になるものは、国内において事業者が行う資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供などや外国からの輸入です。
国内においては、商品の販売や運送、広告など、事業者が事業として対価を得て行う取引のほとんどが課税の対象となります。
消費税の課税対象外のもの
一方、消費税の課税対象外のものに関しては、以下のようなものが挙げられます。
- 土地の譲渡・貸付けなど
- 有価証券・支払手段の譲渡など
- 利子・保証料・保険料など
- 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
- 商品券・プリペイドカードなどの譲渡
- 住民票・戸籍抄本等の行政手数料など
- 外国為替など
- 社会保険医療など
- 介護保険サービス・社会福祉事業など
- お産費用など
- 埋葬料・火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
- 一定の学校の授業料・入学金・入学検定料・施設設備費など
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
※土地の譲渡・貸付けや住宅の貸付けに関しては、一時的なものを除きます。
参照:国税庁ホームページ
そのほか、貨物の輸出や国際輸送・通信など輸出して外国で消費されるものに関しては、「免除取引」として消費税が免除されます。
また、国外での取引や事業者が個人として行う取引、対価性のない取引は「不課税取引」に分類され、課税対象外となります。
(※)…不課税取引の例:給与・賃金の支払い、保険金、共済金、寄付金など
消費税の納税額の計算方法
消費税を納税する前には、納税額の計算が必要です。
消費税の納税額の計算方法には、「原則(一般課税)」と「簡易課税」の2種類があり、事業者の課税売上高などによって使用できる計算方法が異なります。
2021年4月時点、消費税率は標準税率と軽減税率と複数あることから、税率ごとに分けて計算する必要がある点にも注意しましょう。
原則(一般課税)の計算方法
原則(一般課税)の場合、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引く方法で納税額を算出します。
「消費税の納税額」=「課税期間中の課税売上にかかる消費税額」ー「課税期間中の課税仕入れなどにかかる消費税額」
簡易課税の計算方法
簡易課税は、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けた金額を仕入れにかかる消費税額とみなして計算する方法です。
「消費税の納税額」=「課税期間中の課税売上にかかる消費税額」ー「課税期間中の課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率」
みなし仕入率
| 事業の区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業[卸売業] | 90% |
| 第2種事業[小売業等] 小売業/農林漁業(飲食料品の譲渡に関する事業) |
80% |
| 第3種事業[製造業等] 農林漁業(飲食料品の譲渡に関する事業を除く)/建築業/製造業など |
70% |
| 第4種事業[その他] 飲食店業など |
60% |
| 第5種事業[サービス業等] 運輸・通信業/金融・保険業/サービス業 |
50% |
| 第6種事業[不動産業] | 40% |
参照:国税庁ホームページ
ただし、みなし仕入率を使用した簡易課税の計算ができる事業者には、基準期間の課税売上高が5,000万円以下という条件があるので、その点に注意しておきましょう。
消費税の申告方法
消費税の計算が済んだら、次は消費税の申告の準備を進めましょう。
こちらでは、必要な書類や流れなど、申告方法を紹介します。
必要な書類
消費税の申告において主に必要な書類は、以下の通りです。
| 書類名 | 概要 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 消費税課税事業者届出書(基準期間用・特定期間用) | 基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるとき | 速やかに |
| 消費税簡易課税制度選択届出書・簡易課税制度選択不適用届出書 | 簡易課税制度を選択するとき(または選択を取りやめるとき) | 速やかに |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者を選択するとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
「消費税課税事業者届出書」は基準期間と特定期間用の2種類あり、課税売上高が1,000万円を超える場合に速やかに提出する必要があります。
個人事業主と法人でそれぞれ対象の期間が異なりますので、注意してください。
【基準期間】
- 個人事業主…おととしの暦年(1月1日~12月31日)の1年間
- 法人…今期の前々事業年度(2期前)の1年間
【特定期間】
- 個人事業者…その年の前年1月1日から6月30日までの期間
- 法人…原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
「消費税簡易課税制度選択届出書・簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税で計算したい・止めたい場合に必要な書類ですが、前述の通り基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者であることが条件となります。
また、免税事業者が課税事業者になりたい場合、課税期間の初期日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除される「免税事業者」となりますが、支払った消費税が消費者から預かった消費税より高い場合、多く支払った消費税の還付を受けられる可能性があることから、事業者によっては課税事業者を選択したほうが良いケースもあります。
十分な利益が出ていない、設備投資が多い割に売上が上がらないなどの状況にある場合は、検討してみると良いでしょう。
申告・納付の流れ
消費税の納税義務者は、申告期限(※)までに所轄の税務署に確定申告書を提出し、消費税(地方消費税も)を納付する必要があります。
基本的には、消費税の計算、書類の準備、確定申告書の作成、確定申告、消費税の納税という流れになります。
ただし、直前の課税期間の消費税額によっては中間報告・納付が義務付けられています。
また、消費税の申告・納付が期限内に終わらなかったり、間違った申告をしたりすると、不足分の税金を納める必要があるほか、加算税や延滞税が発生する場合もあるので気をつけましょう。
(※)…個人事業者は翌年の3月末日まで、法人は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内
確定申告はオンラインが便利!e-Taxのメリットや手続き方法なども詳しくご紹介!
中間申告・納付
| 直前の課税期間の消費税額 | 中間申告・納付回数 |
|---|---|
| 48万円超400万円以下 | 年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1) |
| 400万円超4,800万円以下 | 年3回(直前の課税期間の消費税額の4分の1ずつ) |
| 4,800万円超 | 年11回(直前の課税期間の消費税額の12分の1ずつ) |
中間申告・納付の条件としては、直近の課税期間の消費税額が【48万超】となっていますが、事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者においては年1回、自主的に中間報告・納付が可能です。
参照:国税庁ホームページ
消費税の負担軽減措置について
事業者の納税事務の負担軽減を目的とした措置が講じられています。
前述した内容が含まれておりますが、主な2つの制度をより詳しくご紹介します。
事業者免税点制度
事業者免税点制度とは、個人または法人における基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者の消費税納税が免税される制度です。
新たに開業・設立された個人事業主や法人のように、基準期間がない場合でもこの制度が適用されます。
消費税の納税が免除される事業者は「免税事業者」と呼ばれ、消費税の申告・納付は不要となりますが、自主的に課税事業者を選択することも可能です。ただし、その場合は原則として2年間は取りやめることができないので注意してください。
簡易課税制度
「簡易課税制度」は、課税売上高から消費税の納税額を計算することができる制度です。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択することができる制度で、事業の区分ごとに設定された「みなし仕入率」を使用して計算します。
上記条件を満たす事業者が「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで適用されますが、事業者免税点制度と同様に適用後2年間は実額計算の原則(一般課税)に変更することができません。
消費税の仕組みを正しく理解して、スムーズな申告・納付を実現しよう!
消費税の納税義務者となり得る事業者においては、消費者とは異なり、仕組みを正しく理解することが重要です。
消費税の仕組みをはじめ、課税の条件や納税額の計算方法などを事前に把握しておくことで、スムーズに申告・納付が行えるでしょう。
申告・納付にはさまざまな準備が必要で、時間がかかる場合もあるので、期日をしっかり確認したうえで早めに進めておくことをおすすめします。
公開日:2021年04月30日