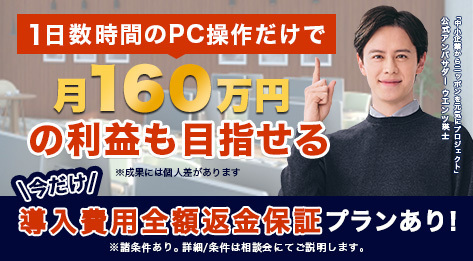自己資金なしで開業資金の融資は可能!自己資金に含まれるものとは
最終更新日:2022年04月26日

開業すると設備購入費、家賃、人件費の支払いといったあらゆる場面でお金の支払いが必要です。
金融機関から融資を受けたくても、「自己資金がないから審査は通らないだろう」と諦めている人は少なくありません。
本記事では自己資金なしで開業資金の融資を受けたい人に向け、おすすめの融資制度を4つピックアップし解説しました。さらに、自己資金として認められるものの一覧や、自己資金なしで融資を受ける際の注意点などもあわせてご紹介しています。
記事を参考に、自身が活用できる融資制度を見つけるきっかけにしてみてください。
開業資金の融資とは

開業融資とは、開業時または開業して間もない人が、事業運営のために必要な資金を金融機関から借りることを言います。借りたお金は、設備の購入や運転資金として利用可能です。
金融機関は日本銀行、民間金融機関、公的金融機関の3つに分けられ、中小企業は公的金融機関である日本政策金融公庫から融資を受けるケースが多いです。
お金を借りる際には審査が必要で、開業する事業の経験年数や自己資金などの要件を満たさなくてはなりません。なお、自己資金とは自分が持っている資金を指し、借入額の10分の1〜10分の3を準備しておくのが一般的です。
自己資金なしで融資を受ける方法4選
自己資金の金額は、融資の審査を通過する上で重要な要素の1つです。ただし、利用する制度によっては自己資金要件が免除される場合もあります。本章では、自己資金がなくても借りられる日本政策公庫の融資制度を4つピックアップしました。
1.新創業融資制度
1つ目は、無担保・無保証人で借りられる新創業融資制度です。新創業融資制度であれば、自己資金がなくても豊富な経験を持っている人や特定の事業をスタートする人なら、自己資金が貯まるまで待たなくても開業できるチャンスを得られます。
| 対象者 | 自己資金の要件 | 資金の用途 | 融資限度額 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| 新事業を開始する人、事業を開始してから税務申告の2期目を終了していない人 | 原則、新事業を開始する人と、事業を開始してから税務申告の1期目を終了していない人は、自己資金として借り入れ額の10分の1以上必要。 | 設備資金、運転資金 | 3,000万円(運転資金1,500万円) | 原則不要 |
ただし、開業する事業に関して一定の経験を持っていたり、「認定特定創業支援等事業」を受けて開業したりするなど要件を満たしていれば自己資金については問われません。
認定特定創業支援等事業とは創業支援事業計画に記載された事業を言い、市町村によって内容が異なります。
2.中小企業経営力強化資金
中小企業経営力強化資金も、自己資金の要件が設定されていない融資制度の1つです。日本政策公庫には、個人・小規模の事業所向けの「国民生活事業」と、一定規模の中小企業を対象にした「中小企業事業」の2種があり、それぞれで審査内容や借り入れ額が異なります。
| 個人・小規模事業者 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 新事業を開始する人、または事業を開始してからおおむね7年以内であり認定経営革新等支援機関から指導・助言を受けている人 | 経営革新や、異分野の企業と連携して市場の創出・開拓をする人、中小企業の会計に関する基本要領」「中小企業の会計に関する指針」を適用している人か適用予定の人など |
| 資金の用途 | 設備資金、運転資金 | 設備資金、運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(この内、運転資金は4,800万円) | 7億2千万円(この内、運転資金2億5千万円) |
| 担保・保証人 | 要相談 | 要相談 |
個人・小規模事業者のなかで無担保・無保証人を希望しており、新事業を開始する人や事業を開始してから税務申告の2期目を終了していない人は新創業融資制度を併用できます。
中小企業経営力強化資金は自己資金の要件が設定されていないものの、対象者が限定的であり定期的な報告が必要な点に注意しましょう。綿密な事業計画を立てることが、審査を通りやすくする重要なポイントです。
3.挑戦支援資本強化特例制度
挑戦支援資本強化特例制度は資本性ローンであるため、借り入れたお金を負債ではなく資本として扱えるのが大きな特徴です。前述した中小企業経営力強化資金と同じく、個人・小規模の事業所向けのものと、中小企業向けで制度の内容が異なります。
なお、挑戦支援資本強化特例制度を利用すると資本金の増額とみなされることから、ほかの金融機関から資金調達をしやすくなるメリットがあります。
| 個人・小規模事業者 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 地域経済活性化の事業を行い、税務申告を1期以上終了している場合は所得税などを原則完納している人で、日本政策公庫が指定する融資制度の対象者であること | 新規事業、経営改善、企業再建などに取り組み、地域を活性化させる雇用効果が認められる事業や、地域にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む人 |
| 資金の用途 | 設備資金、運転資金 | 設備資金、運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円 | 1社につき10億円 |
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 | 無担保・無保証人 |
4.制度融資
制度融資とは資金調達の支援のために、金融機関、信用保証組合、自治体が連携して行う低金利の融資を意味します。審査のハードルが低く、長期間の借り入れができる点が大きな魅力と言えるでしょう。自治体に相談をし、その後指定された金融機関へ行って申し込みをするのが融資の流れです。
制度融資の内容は各自治体により異なるので、会社の住所を管轄している自治体の窓口へ問い合わせてください。
自己資金として認められるもの一覧

これまで、自己資金がなくても受けられる融資制度を解説しました。しかし、自己資金が0円よりも開業資金として手元に確保してある方が審査が通りやすくなるのも事実です。どういったものが自己資金として認められるのか、以下の一覧を参考にしてください。
- 本人名義の預貯金
- 株式や投資信託などの資産を売却して得たお金
- みなし自己資金
- 退職金
- 保険(学資保険、解約返戻金の設定された保険など)
みなし自己資金とは、開業前に設備や事業へ投資した資金を指します。どのような基準で自己資金と判断されるのか、ポイントを解説していきます。
自己資金と判断するポイント
自己資金とみなされるには、出所が確認できる現金であることが重要なポイントです。半年~数年にわたってコツコツお金を貯めている記録が通帳で読み取れれば、「お金の管理ができ返済能力がある」「開業準備を入念に行っている」という証明になるでしょう。
また、すぐに換金できる保険や売却した資産、退職金もお金の出所が明確なので、自己資金として認められる可能性が高いです。審査を有利に進めるためにも、開業資金の用意は念入りに行いましょう。
自己資金として認められない傾向のもの一覧
開業のためにあらかじめコツコツ貯蓄していたお金や、出所が明確なものは自己資金として認められると説明しました。反対に、自己資金とみなされないお金にはどのようなものがあるか、例をご紹介します。
- タンス預金
- 返済義務がある借りたお金
- 出所の分からないお金
- 突然振り込まれた大金
なぜ、上記のお金が自己資金にならないのか、理由を確認していきましょう。
自己資金にならない判断基準
出所が分からないものや返済義務があるものは、自己資金とみなされません。たとえば、借りたお金は返済義務があるため借り入れに該当します。融資の審査直前になって一気にお金が振り込まれている場合、一時的に誰かから借りた見せかけのお金と判断される確率が高いです。
「お金を持っている=自己資金がある」という訳ではないので、融資を考えている人は計画的にお金を貯めるよう心がけましょう。
自己資金なしで融資を受ける際の注意点
自己資金がなくても融資を受けて開業資金を確保できるのは魅力的です。一方、自己資金なしで融資を受ける際には、金利が高くなったり融資額が少なくなったりするなどのデメリットもあります。それぞれの注意点を詳しく解説します。
金利が高くなる
1つ目の注意点は自己資金がある場合と比べ、金利が高くなる傾向にあることです。一般的に金融機関から融資してもらうときは、金利が設定されています。日本政策公庫の融資制度は比較的、金利が低いとされていますが、自己資金がなければ上限の金利を設定される可能性があります。
どうしても開業資金が必要な人にとっては、金利が少し高くなったとしてもまとまったお金を借りられるのはメリットが大きいでしょう。自身の現状と返済のバランスをよく考え、本当に借りるべきか検討した上で融資を申し込みましょう。
融資額が少なくなる
自己資金なしで開業融資を申し込む際は。融資額が低く設定されることも留意しておくべきポイントの1つです。もし希望額より融資が少なければ、事業の運営に支障が出るおそれもあります。開業を決意したらすぐに貯蓄を始めて、少しでも多くの資金を手元に用意しておくのが賢明でしょう。
自己資金がなくても諦めず調べてみよう
開業時に自己資金を保有しておくことが望ましいとは言え、開業を決意したタイミングによっては自己資金の確保が難しいこともあるでしょう。コツコツと自己資金を貯める開業時期を伸ばす方法もありますが、今回ご紹介した自己資金なしの融資制度を利用するのも有効な手段の1つです。
事業内容や経験年数といった決まりはあるものの、条件が揃って審査が通れば金銭的な余裕を持って事業を運営するのに役立ちます。自己資金がないので開業を諦めるのではなく、日本政策公庫の融資制度を調べたり、使える助成金や補助金がないか確認してみましょう。
開業資金を借り入れたいと考えている人には、借り入れ先や注意点をまとめたこちらの記事も参考にしてください。
公開日:2022年04月26日