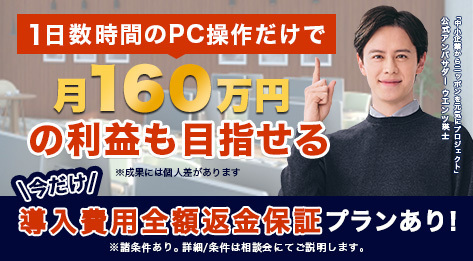市場規模4兆円!飲食フランチャイズについて知る!
公開日:2016年02月22日

街のいたるところで目にする飲食フランチャイズチェーン。
「あの居酒屋って、どれくらい儲かっているのかな?」と、経営について考えたことがある方も多いのでは?
「ついに駅前に〇〇ができた!」「私の好きな居酒屋は〇〇!」
など、今や生活には欠かせない存在となった飲食フランチャイズですが、なんとコンビニエンスストアを上回るほどの店舗数があるんです。
今なお、多種多様な業態が生まれる飲食ビジネスについて、市場規模から業態の種類、リスクにまで迫り、最新の飲食フランチャイズ事情をお届けします。
目次
1. 飲食フランチャイズとは?
1-1. 飲食フランチャイズの市場動向:チェーン数は3年連続増加
1-2. 飲食フランチャイズの開業資金について
1-3. 飲食フランチャイズのランニングコストについて
1-4. 飲食フランチャイズの売上について
2. 飲食フランチャイズと他業種との比較
2-1. 飲食フランチャイズとコンビニとの比較
2-2. 飲食フランチャイズと幼児教育・保育園との比較
2-3. 飲食フランチャイズと他のサービス業との比較
3. 飲食フランチャイズの3種類の業態
3-1. 飲食フランチャイズの業態①:ラーメン
3-2. 飲食フランチャイズの業態②:居酒屋
3-3. 飲食フランチャイズの業態③:お弁当
4. 飲食フランチャイズで起こりうるリスク
4-1. 悪天候による原価の高騰
4-2. ランニングコストが大きくかさむことも
5. まとめ:飲食フランチャイズの成長の秘訣
1. 飲食フランチャイズとは?
飲食フランチャイズについて、市場動向、開業資金、売上面からご紹介します。
1-1. 飲食フランチャイズの市場動向:チェーン数は3年連続増加
外食産業のフランチャイズについて、まずは市場規模からみていきましょう。
2015年3月時点で前年比+12チェーン、415チェーンを展開しています。店舗数にすると58,910店舗!3年連続で増加傾向です。増える店舗数の中を勝ち抜く競争力をつけるべく、飲食フランチャイズの業態は、時代の流れを汲み取る動きをみせています。
「居酒屋」系の飲食フランチャイズは、従来の低価格志向から、専門性の高い業態へと関心が移りつつあります。
また、ドトールコーヒーをはじめとする「カフェ」業態のフランチャイズは、店舗改装や新メニュー開発を積極的に展開し、各チェーンともに好調。
近年の肉ブームをとらえた熟成肉のステーキ店や、短時間・低価格で店舗で提供するピザ屋など、新業態も着実に芽吹いています。※1
1-2. 飲食フランチャイズの開業資金について
飲食業のフランチャイズは、業態により開業資金も様々です。
「郊外のロードサイドのレストラン」「省スペースで開業できる居酒屋」「弁当のようなテイクアウト専門店」など、同じ飲食ビジネスでも業態によって開業資金は異なります。
レストランや大型居酒屋店のように、1,000万円以上の開業資金がかかる飲食チェーンの場合、リターンは大きいが初期投資でまとまった金額も必要なため、法人が新規事業として加盟するケースがよく見受けられます。
一方、数百万円で開業ができる弁当屋や、居抜き物件を活用することで初期コストを抑えられる居酒屋、レストランなど、加盟オーナーの開業時の負担を少しでも軽減するプランがあるのも、飲食店の特長です。
1-3. 飲食フランチャイズのランニングコストについて
家賃や水道光熱費をはじめ、まとまったランニングコストがかかる外食産業。
ロイヤリティーについても、各ブランドに応じて様々な設定がされています。売上の3~5%に設定しているフランチャイズ本部が多くありますが、坪数に応じた設定や、店舗使用料としてなど、「月額固定制度」を取り入れる飲食フランチャイズも増えてきています。
業態に合ったロイヤリティー設定がされているかも、本部を見極めるポイントのひとつです。
1-4. 飲食フランチャイズの売上について
客単価と回転数に応じて売上が決まる飲食ビジネス。そのため、業態によって月商1,000万円以上が十分に狙えるのも、外食産業の魅力です。
大型店を開業するメリットはまさに、年商1億円超えに挑戦できることでしょう。一方、小規模店舗の場合は、少人数で店舗を運営できるため、高利益率になりやすい、という特長もあります。
「どのような立地で勝負したいのか」「どんな商品を提供したいのか」など、店舗に立つ姿を想像しながら、比較検討してみることがおすすめです。
2. 飲食フランチャイズと他業種との比較
「フランチャイズは、飲食業だけしかないの?」そんなふうに思う方も多いと思います。
フランチャイズは、様々な業種で使われている経営手法です。
2-1. 飲食フランチャイズとコンビニとの比較
小売業の代名詞とも言えるコンビニフランチャイズ。
最大手の「セブン-イレブン」を筆頭に「ローソン」「ファミリーマート」「ミニストップ」が業界を牽引しています。店舗数は2015年12月時点で53,544店舗。飲食フランチャイズと同じくらいの店舗がある業界です。
契約期間は平均10~15年と比較的長め。ロイヤリティーは売上総利益、総荒利益高に対しスライドチャージを乗じた金額で設定しているケースがあります。
開業資金は、1,000万円以上が必要な飲食店に比べ、平均250~300万円と、低く設定されています。※2
2-2. 飲食フランチャイズと幼児教育・保育園との比較
「待機児童」が社会問題となるように、核家族化の進行、共働き世代の増加から、保育園・幼稚園への需要は高まりをみせています。
従来の幼児教育に加え、近年では英語教育に対応している幼稚園も増加。中には、国の給付金で運営できるものもあり、注目を集めているフランチャイズです。
初期投資は500~1,500万円とさまざま。飲食フランチャイズと同等の費用がかかります。
年商3,000万円以上が狙えることに加え、社会貢献性も高いことから、教室に通う保護者の方からも加盟希望がある業種です。
2-3. 飲食フランチャイズと他のサービス業との比較
店舗数・売上高共に伸長している「学習塾」ビジネスをはじめ、ハウスクリーニングや介護サービスなど、多様なサービスが市場を伸ばしています。
サービス業のフランチャイズは84チェーン(2015年3月時点)。店舗数・売上共に飲食フランチャイズの6割程の規模となります。
例えば、介護施設へ宅配弁当を届けるなど、サービス業は外食ビジネスとの相乗効果が生まれやすい業界でもあるため、飲食フランチャイズと合わせて動向を注目するとことをおすすめします。※3
3. 飲食フランチャイズの3種類の業態
3-1. 飲食フランチャイズの業態①:ラーメン
飲食フランチャイズの中でも人気業態のひとつが「ラーメン」ビジネス。
市場規模6,000億円と呼ばれる巨大ビジネスの中で、ラーメン業態のフランチャイズチェーン全体の売上は2,365億円!飲食フランチャイズ市場全体の実に40%近くの売上シェアを占めています。
家系ラーメン、つけ麺、豚骨ラーメンなど、他社との差別化を図るコンセプトを各フランチャイズ本部が次々に打ち出しているのが、ラーメン業界の特長です。
のれん分け制度を起用し、屋号を自分でつけられる本部も登場するなど、オーナーの個性が反映しやすいフランチャイズも増えています。※4
3-2. 飲食フランチャイズの業態②:居酒屋
居酒屋のフランチャイズは、ラーメンに次ぐ、4,000億円を超える 市場規模を持つ一大外食ビジネスです。
居酒屋経営と言えば、その魅力のひとつが「客単価」です。ラーメン店の平均客単価が800円であるのに対し、居酒屋の場合は2,500~3,000円と、3倍以上になります。
他の飲食ビジネスに比べ、お客様からの予約注文も入りやすく、事前に売上目途が立ちやすいのも特長です。
居酒屋と言えばある程度広い物件が必要というイメージもありますが、近年は小スペースで開業できる居酒屋業態も続々と誕生しています。個人でも開業しやすい居酒屋フランチャイズ業態が増えています。※5
3-3. 飲食フランチャイズの業態③:お弁当
都内では、2軒に1軒が一人暮らしと言われるほど、単身世帯が増えています。そんな中、お弁当をはじめとした中食事業の伸びが注目を集めています。
中食フランチャイズのチェーン数は、22チェーンと他の飲食フランチャイズに比べて少ないものの、4,000億円近くの市場規模を占めています。
昼はお弁当を提供し、夜は居酒屋業態を開く二毛作展開や、高齢者向けの宅配弁当など、多様な販売スタイルを持つお弁当フランチャイズ。アイデア次第で新しい取組みが生まれやすいのも特長です。※6
4. 飲食フランチャイズで起こりうるリスク
飲食店を経営する上で考えられる2大リスクについて紹介します。
4-1. 悪天候による原価の高騰
お客様に美味しい料理を提供し、気づけば常連様が増えている。
そんな「人と人」との繋がりが魅力の飲食業ですが、経営をする上では当然リスクも伴います。
その一つが「原価の高騰」。悪天候や狂牛病をはじめ、疫病が発症すると、とたんに原価は高騰します。飲食は人が口にするものですから、品質管理は最も重要なこと。
フランチャイズの場合、本部が仕入れ先の管理や調整をおこなってくれるケースが多いので、個人経営に比べ店舗運営に専念しやすい環境ではあるものの、世間の動きを注意深くみておくことが重要です。
4-2. ランニングコストが大きくかさむことも
サービス業や小売業に比べ、飲食業はある程度大きな店舗を用意する必要があるフランチャイズです。
店舗面積が広くなるほど、多くのスタッフや食材、家賃や光熱費が発生します。そのため、ランニングコストが負担になるケースもあります。
一般的に、損益分岐点売上高は「ランニングコスト×(1÷粗利益率)=損益分岐点売上高」と言われています。飲食ビジネスを検討する場合は、事前にシミュレーションを立ててみると良いでしょう。
5. まとめ:飲食フランチャイズの成長の秘訣
飲食フランチャイズは着実に成長を続けている業界です。
今なお伸長している最大の理由、それは「時代への適応力」にあります。
低価格路線からオリジナル性への変更、高齢者向けの宅配弁当サービス、店舗改装によるブランドコンセプトの刷新など、社会の流れをいち早くキャッチし、お客様の心をつかむ姿勢が、飲食ビジネスの勢いを後押ししているのです。
時代を店舗に取り込む経営戦略、お客様の満足を勝ち得る店舗運営。この両輪をフランチャイズ本部と二人三脚で回すことで、理想の飲食ビジネスを追求してみてはいかがでしょうか。
※1~6出典:「日本フランチャイズチェーン協会」
http://www.jfa-fc.or.jp/particle/19.html
この記事を読んだアナタにおすすめ
「FC比較ネット」営業担当が語る!加盟開発成功の極意とは?(飲食編)