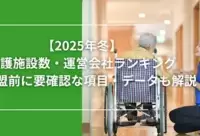コンビニ経営のメリット・デメリットとは?オーナーの仕事、成功のポイントは?
最終更新日:2024年09月20日

「コンビニ経営」「コンビニオーナー」という言葉、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
独立開業を目指す際の選択肢として人気のコンビニ経営について、さまざまな角度から検証していきます。
1 コンビニオーナー、経営の仕事って?
普段、何気なく利用しているコンビニ。しかし、コンビニオーナーがどんな仕事をしているのか、意外と知らないのではないでしょうか。そこで、コンビニオーナーがどんな仕事をしているのかをご紹介します。
1-1 コンビニ経営者は何をしている?
コンビニの多くは、24時間営業を行っています。だからといって、オーナー自ら24時間店頭で仕事をしているというわけではありません。オーナーは「経営者」なので、主な仕事は店舗の「経営」となります。
「経営者」としての仕事は大きく2つあります。
1.資金繰り
これは、店舗を経営する上でもっとも重要なこと。日々の売上管理はもちろん、仕入れや人件費、光熱費、家賃などの経費の管理など、お金に関することを行います。
2.人材育成
いくら店舗があっても、そこで働く従業員がいなければ話になりません。オーナー自ら店舗で働くこともありますが、24時間365日働くことは無理。そこで重要になるのが、従業員の育成です。コンビニはアルバイト店員がメインとなりますが、正社員を雇用するケースもあります。経営者としては、この従業員たちの育成も必須の仕事です。
1-2 コンビニの店長とオーナー(経営)は違う役割
コンビニには「店長」と呼ばれる人がいます。あまりコンビニ経営について分からないと、「店長=オーナー」と考えがちです。しかし、実際には店長とは別にオーナーがいます。
「オーナー」とは、その店舗の経営者・最高責任者で、経営全般についての仕事を行います。
一方「店長」は、店舗の現場責任者です。工事現場における現場監督のようなものです。
レストランではオーナーとシェフが別な人ということもありますが、基本的にはそれと同じことです。
最近では、1人のオーナーが複数のコンビニ店舗を経営するケースも増えています。その場合は、店舗ごとに店長を雇っていることがほとんどです。
1-3 コンビニ経営のカギは従業員の教育
コンビニオーナーとして、安定した経営をするために重要なのが、先述した「人材育成」です。きちんと働いてくれる従業員がいなければ、コンビニ経営は破綻してしまいます。
また、「店舗を大きくしたい」「店舗数を増やしたい」と考えているのならばなおさらです。まず、「自分が現場に出なくても良いシステム」を、なるべく早い段階で確立することが重要となります。
アルバイトの確保はもちろんですが、「店長」あるいは「店長候補」と呼ばれる人材を発掘し、確実に店舗運営ができるように教育することが、コンビニ経営の成否を分けると言っても過言ではありません。
コンビニ以外で自分のお店を持ちたい方はこちらをチェック
2 フランチャイズでのコンビニ経営とは?
コンビニは、フランチャイズビジネスの中でも人気業種です。では、コンビニ経営の魅力はどんなところにあるのでしょうか?
他のフランチャイズビジネスとの違いについて考えてみましょう。
2-1 フランチャイズの仕組みについて
コンビニ・フランチャイズについて考察する前に、まずは「フランチャイズとは何か?」について簡単に説明します。
フランチャイズは、本店がありその支店を展開する、いわゆるチェーン店とはまったく違うビジネスです。
大きな違いは、誰にでも門戸が開かれており、誰でも加盟でき開業できるという点でしょう。自分で経営などをしたことがないサラリーマンでも、思い立ったら「オーナー」「経営者」になれるのが、フランチャイズです。
そして、フランチャイズビジネスは強いネームバリューを持っています。まったくのゼロから始める個人商店は、長い年月をかけて「信用」を得なければなりません。しかしフランチャイズの場合は、すでに本部が持っているネームバリューを使えます。つまり、開業と同時に「信用」も得ることができるのです。そこがフランチャイズビジネスの画期的な点なのです。
コンビニ以外のフランチャイズを探す
2-2 コンビニフランチャイズ経営の特徴
では、コンビニ・フランチャイズは他のフランチャイズと何が違うのでしょうか?
フランチャイズと呼ばれる事業は、非常に多岐にわたります。街を歩けば、その大半がフランチャイズ展開されている店舗です。その代表格がコンビニなのです。
コンビニ・フランチャイズの一番の特徴は、「ブランド力」です。大手コンビニの名前を知らない人はほとんどいないでしょう。そして、そのブランド力に合わせて、本部のサポートがしっかりしていることも特徴です。
コンビニ・フランチャイズは、長い歴史があります。そのなかで培われた経験と情報をもとに、開業前はもちろん、開業後もオーナーへの手厚いサポートが整っていることが、最大の魅力であり、安心感になっていると言えるでしょう。
2-3 現在のコンビニ業界の市場規模と傾向
街を歩けば目にするコンビニ。その市場規模はどうなっているのか、開業する側にとっては一番気になるところではないでしょうか。
日本フランチャイズチェーン協会の調査によるデータでは、2019年度のコンビニの国内市場は11兆円を超え、伸び続けています。
地域密着型のスーパーや商店街などが姿を消していく中で、コンビニはその代わりとしての立ち位置になってきています。現在では若者だけではなく高齢者もターゲットに市場拡大を図っています。
高品質で安価なプライベートブランドの拡大、高齢者への宅配事業などが今後の市場拡大のカギとなるでしょう。
3 コンビニ経営のメリット
フランチャイズ業界でも人気のコンビニ。そのメリットについて解説します。
3-1 コンビニ経営は流行に左右されない
「長く経営できるか」は、独立開業の際の不安材料のひとつです。開業時は流行の最先端だったとしても、その流行が過ぎてしまえば1年で経営が行き詰まってしまうこともあります。しかし、コンビニにはそのような心配はありません。
なぜなら、コンビニで扱う商品の大半が、食料品や日用雑貨などの「日用品」だから。日用品が人の生活から不要になるということはあり得ません。特に食料品は、人間が生きていく上でもっとも必要なものであり、「食べもの商売は強い」と昔から言われている所以です。
つまり、流行に関係なく、いつでもすべての人に必要なものを扱っているから、コンビニは長く経営できるのです。
3-2 どんどん便利になることで成長するコンビニ市場規模
いつもそこにあるコンビニ。毎日のように利用していると気づきにくいかもしれませんが、少しずつ進化しています。
・プライベートブランドの拡大
各コンビニがさまざまな企業と提携して開発されている「プライベートブランド」が、食料品をメインに増えています。プライベートブランドの商品は、高品質ながらも低価格なものが多いため、人気商品となります。各コンビニで近年はプライベートブランド商品に力を入れており、今後もさらに拡大していくと思われます。
・高齢者向け宅配事業の拡大
コンビニがプライベートブランドと共に力を入れているのが「宅配」です。利用者のメインターゲットは「高齢者」。自力で買い物に来られない高齢者にとって、幅広い商品を扱うコンビニの宅配はとてもありがたいシステムです。これからの高齢化社会を考えると、今後の規模拡大が見込めます。
3-3 コンビニ経営は地域の人との交流ができる
商店街など地域密着型の個人商店がメインだった時代は、お店の人と客が声を掛け合うといったことはよく見られる光景でした。しかし、大型スーパーの時代を迎え、そのような光景は見られなくなりました。しかし大型スーパーと違い、コンビニはより地域密着型の事業を展開することが可能です。
宅配事業は、その根幹になり得るものです。店員が個別に商品を宅配することで、高齢者の無事を確認できるというメリットが生まれます。また、店舗側にとっても宅配先がリピーターとなり、末長い付き合いとなります。
そんないい関係を築けると、客が客を紹介してくれるようになります。商品だけではなくサービスも充実させることで、販路が拡充していきます。
「地域の人から愛されるサービス」を手がけたい方はこちらをチェック
3-4 コンビニ経営は多店舗展開を目指せる
コンビニ経営の大きな魅力のひとつとして、「他店舗経営ができる」という点が挙げられます。1店舗から2店舗、3店舗と徐々に店舗が増えていくというのは、経営者にとっての大きな夢です。
コンビニ経営に慣れてくると、複数の店舗経営が可能です。そこで重要なのが、店舗を任せられる「店長」の存在。繰り返しになりますが、人材育成がうまくいけば、多店舗経営も夢ではないのです。
4 コンビニ経営のデメリット
人気のコンビニ経営ですが、メリットばかりではありません。ここでは、デメリットについて解説します。
4-1 採用がうまくいかない場合でも、お店を運営しなくてはならない
優秀な人材を確保し育成ができれば、経営は安定します。しかし、現実問題として人材が見つからなかったり、見つかってもすぐにやめてしまったりといったリスクが存在します。
そのような場合でも、コンビニは営業しなければなりません。24時間365日、いつでも開いているのがコンビニの最大の特徴。従業員がいなくても、営業を続けるのがコンビニの宿命なのです。
不測の事態に備え、オーナー自らはもちろん、家族や親族なども稼働できるように準備をしておくことが重要です。
4-2 ブランド力の衰えの可能性
コンビニの一番の強みは、ブランド力です。大手コンビニの名前は老若男女が知っています。しかし、どんなに有名企業でも時流による浮き沈みというものがあります。
コンビニに限った話ではありませんが、本部の姿勢や営業方針がしっかりしていないところは、いずれブランド力に陰りが出てくるもの。そのためにも、大きなブランド力を持ち、本部のサポートがしっかりしているところを選ぶことが肝心です。
手厚いサポート制度があるフランチャイズを探す
4-3 契約期間が長期間のブランドがほとんど
コンビニ・フランチャイズが他のフランチャイズと大きく異なるのが、「契約期間が長い」ということ。どのコンビニ本部でも、10年、15年といった長期契約がほとんどです。そのため、1年やそこらで辞めるというわけにはいきません。
オーナーの多くは、商売が軌道に乗るまで2〜3年はかかると言っています。この年数については、オーナーの経営手腕で変わってくるものです。
経営が軌道に乗るまでに期間がかかるということは、起業の際に肝に銘じておきましょう。これはコンビニに限らず、どんな商売でも一緒です。
5 コンビニ経営の成功ポイントとは?
起業するからには、成功させたい。そう思うのは当然です。そこで、成功のためのコンビニ経営の基本的な心構えを解説します。
5-1 接客第一!それを生む教育と、雰囲気づくり
商売の基本は、お客様ありきです。特にコンビニは、幅広い年齢層が対象となります。どんなお客様に対しても公平で気持ちのよい接客をすることが基本中の基本です。
経営者として、スタッフ教育で一番大切にすることは、接客態度。大きな声で明るい挨拶は当然のこと。店内を明るい雰囲気に感じさせる効果があります。
また、お客様の顔を覚え、世間話をするくらいの気配りも重要。きっちり仕事をこなすことはもちろんですが、プラスアルファの部分で「感じのよいお店」という印象を与えることが重要です。
「人と接する仕事」である飲食業で起業したい方はこちらをチェック
5-2 商品ポップなどで積極的に売りたい商品をアピール
「店長のオススメ!」など、商品に掲げるポップは効果絶大です。整然と商品が並ぶコンビニでは、個々の商品のアピールができないと思いがちですが、そんなことはありません。
特に、似たような商品の場合はお客様がどれを選んでいいのかわからないといったこともあります。そんなときに、ポップでアピールをすれば購入したくなるもの。楽しく、品のよいポップは、店内の雰囲気を明るくする効果もありますよ。
5-3 コンビニフランチャイズ本部とよい関係性を築き、共に成長していくこと
フランチャイズに加盟したのならば、本部を有効活用しない手はありません。本部に積極的に意見を述べ、不具合があるところは改善していくというような姿勢を見せれば、本部からも一目置かれる存在になることでしょう。
本部が認めてくれれば、自ずと力を入れてくれるようになります。複数店舗を持ちたいといった希望も積極的に聞き入れて、優先的に動いてくれることも。
本部とよい関係性を築くことは、フランチャイズでの成功の近道なのです!
6 コンビニオーナーに聞く「成功の秘訣」
ここでは、実際にコンビニ・フランチャイズで成功を収めているオーナーの声を聞いてみましょう。
ローソンで5店舗を経営する稲葉康彦オーナーは、本部の手厚いサポートが成功へのモチベーションとなっていると語ります。
「マチカフェなど他社との差別化を図る商品開発はもちろん、本部が店舗経営に対して親身にサポートを行ってくれます。研修もオーナーやクルー向けに定期的に開催されますし、近隣店舗のオーナーが集まって情報交換できる交流会もあります。一体感を感じながら経営できるのはローソンならではの魅力でしょう」
また、結果を出している店舗に対して、新しい設備やコンテンツを優先的に導入してくれることがあるので、がんばろうという気持ちが沸いてくるそうです。
ローソンならではのサポート体制で多店舗経営の夢を実現しました
セブンイレブンのオーナーである稲澤真二さんは、スタッフ教育の重要性についてこう話しています。
「私たちはセブン-イレブンの基本4原則『品揃え』『鮮度管理』『クリンリネス』『フレンドリーサービス』を日々意識してがんばっていこう、と積極的に声をかけ、まずは基礎をしっかりと押さえて土台を固くする方針をとっています」
多店舗経営も視野に入れている稲澤さん。やはり人材育成の重要性を理解しているようです。
7 まとめ
コンビニのオーナーは、店長とは異なり、お店の経営がメインの仕事です。お金周りのことはもちろん、従業員の育成も重要です。
コンビニ・フランチャイズは、本部のブランド力を最大限に利用できるため、成功しやすいこと、そして長い歴史を持つフランチャイズビジネスだけに、開業前後のサポートが充実しています。
そして、時代の流行に左右されにくいため、長く経営ができるのも魅力。ただし、従業員の採用・育成がうまくいかないという場合でも店舗を休むことができないというデメリットがあることに注意しましょう。
成功の秘訣は、本部との良好な関係を築くこと。そして、従業員の育成も大切。地域に密着した経営をすることで、誰からも愛される店舗になれば、自然と経営は安定するはずです。
自分の条件に合ったフランチャイズを探す
公開日:2018年04月19日